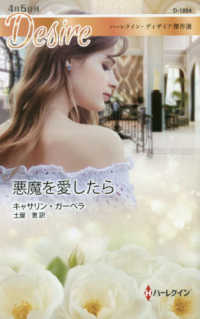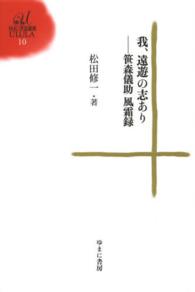内容説明
本書では、子どもに柔軟な心を育てるための心の成長段階に応じた接し方のポイントを、幼稚園・保育園や家庭での27の事例を通して具体的に紹介します。子どもの理解に必要な、子どもの心の成長の段階や環境との関わりについてもくわしく説明します。
目次
第1章 子どもの「心」の成長と環境(心は育てられる?;子育ての移り変わり―子どもの育ちをうながす環境;心の成長表;心の成長に応じた「柔軟な心」を育てる接し方)
第2章 子どもに「柔軟な心」を育てる具体的な接し方(乳児期―誕生から十二~十八カ月ごろまで;幼児期(前)―十二~十八カ月ごろから三~四歳(第一反抗期)ごろまで
幼児期(後)―三~四歳ごろから六歳ごろまで
児童期(前・後)―六歳ごろから十四~十五歳ごろまで)
著者等紹介
諏訪耕一[スワコウイチ]
1937年愛知県豊田市に生まれる。1965年愛知県公立中学校教諭に。1994年長野県に不登校児・者の回復施設「浪合こころの塾」を設立。2003年同じ村内に、塾に代わり「浪合こころの相談室」を開設(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
IGBB
1
アドラーの「個人心理学講義」を読んだ後ということもあってか、スラスラ内容が頭に入ってきた。表紙だけを見ると育児書のように見えるが、書かれている内容は、特に第1章は、骨太の教育論である。印象に残ったのは次の一節である。●「まっ、いいか」というような曖昧さを認められる、柔軟性のある心を持った人は、対人関係で約束の実行を深追いせず、妥協できます。そのため、集団内では敵をあまり作らず、人を追い詰めることもしませんから、相手から激しい追求を受けることが少なく、「いじめ」に関係することも減るのです。2021/04/01
nori
0
著者はもと公立中学校の先生不登校児の問題に深く関わっているらしい。 そのネットワークからかいろんな人の協力を得て事例をたくさん書いてあるのは良かったが、個人的にはそんなに参考にならなかった。 たぶん私が求めていたのは具体的な事例ではなくて、著者のような視点から編み出した子育て全体を通しての傾向や言葉のまとまりを読みたかったからだと思う。2020/03/11
-

- 電子書籍
- 復讐代行アプリ ~1タップで処刑します…
-

- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版別冊 0歳からの…