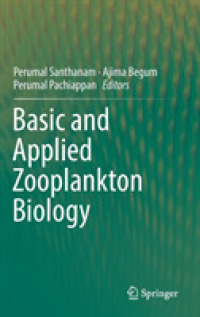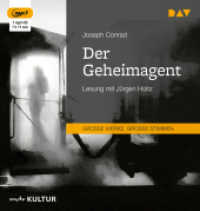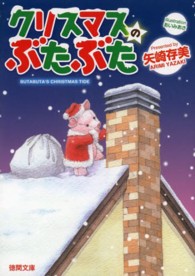内容説明
『国語科授業づくりの深層』に続く「深層」シリーズの第2弾!私立小学校教師と公立中学校教師という立場も年齢も異なる二人の優れた現役教師が、お互いを触媒にして化学変化を起こしながら、今日の教育現場の重要課題について縦横無尽に語る。
目次
第1章 対談 学級づくりの深層
第2章 次年度に崩れる子どもたち
第3章 同調圧力の構造
第4章 今どきの子ども理解
第5章 授業づくりと学級づくり
第6章 学年づくりと学級づくり
第7章 語られない失敗事例―教師の力量形成のために
著者等紹介
多賀一郎[タガイチロウ]
追手門学院小学校講師。神戸大学附属小学校を経て私学に永年在籍。元日本私立小学校連合会国語部全国委員長。親塾での保護者教育、若手のためのセミナー他、公立私立の小学校で指導助言をしている
堀裕嗣[ホリヒロツグ]
1966年北海道生。1991年札幌市中学校教員として採用。1991年、「実践研究水輪」入会。1992年、「研究集団ことのは」設立。現在、「研究集団ことのは」代表、「教師力BRUSH‐UPセミナー」顧問、「実践研究水輪」研究担当を務める傍ら、日本文学協会、全国大学国語教育学会、日本言語技術教育学会にも所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えぬ
3
辛辣な言葉も多いが、こういう本音で建前ばかりじゃなくて書いた本っていいな。響くものが多い。2016/02/21
江口 浩平@教育委員会
3
やはり堀先生と多賀先生の対談は面白い。【学級経営が成功すれば、そこには「洗脳」の側面があるのではないか】というフレーズは、現場ではタブー視されている感があるものの、我々教員が少なからず抱いている気持ちを代弁してくれているように感じた。今どきの子ども理解や同調圧力についての考察なども、現役教員ならではの鋭さがあり、読んでいて共感したり驚かされたりするところが多かった。ぜひ多くの教員に読んでいただきたい一冊だった。2015/12/05
mori
2
対談が面白い。そこまで言うのね…という箇所もあった。著者の二人に共通していたのは、「理解できないがわかろうと努力すること」「畏れ」 分かったつもりになっていないか自戒したい。「次年度の荒れ」「職員室のカースト」「洗脳」小学校教員には耳の痛い指摘もあり。システムが変わるのを待つ前に、まずはオープンにし情報を共有すること。これならできるかもしれない。学級づくりは最終的に個を育てること、学級づくりと学年づくりの類似性。小学校と中学校のシステム、考え方、メリットとデメリットを考える。失敗談の章があるつくりも面白い2015/11/15
にくきゅー
0
自分の行いが他者にどう影響するのか、これをどこまで広く深く考えることができるかがその教師の力量を示すのではないかと思った。2017/08/06
アスカ
0
自分はもう若手と言われる年齢ではないので、読みながら、そうだよねそうだよねと共感することの方が多かった。でも思い返したら、若手と言われていた頃から、こういう考え方を持っていた気がする。それは、自分では無意識に自然と身についた考え方と思っていたけど、堀先生が書かれていた通り、初任の頃にたくさんのことを教えてくれた先生の影響が大きいのかもしれない。自分は周りの人たちに恵まれていた。自分もまだまだだけど、もうこういうことを若い人たちに伝えていく方になっていくんだな。もっとコミュニケーションとらないとね。2016/01/09