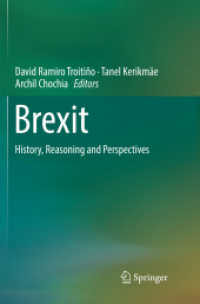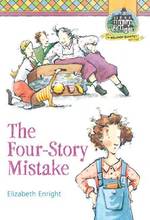内容説明
メディアリテラシーを身につけた賢い情報受信者、発信者になるために。
目次
はじめに:「本物の情報」を求めて
だましのテクニックを見破れ―下心がいっぱい
何がニュースか―送り手と受け年の関係
ジャーナリストの仕事場―好奇心を全開にし現場へ
ジャーナリズムってなに?―もしもそれが無かったら
客観報道とは―伝えることのむずかしさ
これこそが特ダネだ!―スクープの意義
人権と犯罪報道―報道被害を減らすには
情報源を守る―都合の悪いことは隠される
誰もがジャーナリスト―ネット時代のメディアのあり方
情報は一人歩きする―あふれる情報の時代に
思い込みの壁―海外ニュースは遠い存在?
愛国心はほどほどに―冷静さを取り戻す道
終わりに:「世論」が暴走しないために
著者等紹介
三浦準司[ミウラジュンジ]
ジャーナリスト。1948年東京生まれ。1972年東京大学経済学部卒業。同年、共同通信社に入社。京都支局、社会部、外信部。1985‐8年ナイロビ支局長、1991‐4年ワシントン特派員、1999‐2001年ロンドン支局長、2008‐11年記事審査室長、2011‐6「英語子ども新聞」編集長など努める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
84
副題に「フェイクニュースを見分けるには」とつけられていますが、内容はフェイクニュース対策というよりメディア側の説明に終始しています。フェイクニュース対策としては"いろんな意見に目を向けましょう"というようなありきたりの事しか書かれていませんでした。"メディアのニュースを鵜呑みにしない"イコール"メディア・リテラシーを高める"ということなのでしょうが、フェイクなニュースをどうやって見抜くのか具体的なヒントが欲しかったです。また、では、正しい情報を得るにはどうすればよいのか、そのアドバイスも欲しかったです。2023/08/22
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
71
昔は当然の真実だと信じられていたニュースが今はフェイク。一体何を信じれば良いのだろうか。ジャーナリストは現場を踏み臨場感を味わい真のニュースを発信するが、時に歪められてしまう。有名なマックでやけどし大金を手にした老婦人のニュース。後日談がなく失意の果てに亡くなられたという。特ダネで煽り「この人が犯人だ」と決めつけ、違っていても後から訂正しない。その例が松本サリン事件の河野さん。新しければ珍しければという発想自体を止めてもらいたい。10代向けだが大人が読んでも面白い。多少ジャーナリストを贔屓している感あり。2023/07/30
hk
21
【趣旨】15世紀、グーテン君が活版印刷術を汎用化させ、民衆に「知の受信」が解放される。そして20世紀末、IT革命によって民衆に「知の発信」までもが解放された。現下のウェブ空間には営利メディアだけではなく一般人もが参加し、玉石混交の膨大な情報で満ち溢れている。発信者が営利を旨としないのは、資本の意向に左右されないという側面においてはよいことだろう。一方で発信者の匿名性が強まったことにより、誇張や曲解情報が広まる危険性が高まった。そんな状況下においては、民衆が各々情報発信と受信双方の目利きになる必要性がある。2017/10/23
テツ
19
こども向けに「ジャーナリストとは、ジャーナリズムとはなんぞや」ということをわかりやすく説明してくれている。全ての情報には発信者による何かしらのバイアスがかかっているという大前提を忘れないこと。それを踏まえた上で自分自身とは異なる意見の持ち主が齎す情報も避けることなく受け入れ吟味し、自分の頭でしっかりと考えて思考を組み立てていくこと。一つの情報だけを基に世界を眺めてはいけない。全ての悲劇はそこから始まるのだから。大人が読んでも自分自身の情報との向き合い方について今一度考えさせてくれる良書。2020/04/17
マ・クベ
17
なるほど!ニュースについて、考えさせられました。やっぱり、我々は、情報に操作されている。すべてを鵜呑みにせず、情報を精査して、受け止めないと行けないと思います。2018/03/20
-
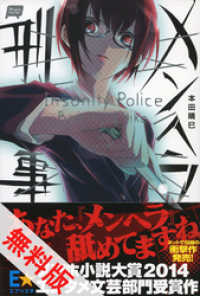
- 電子書籍
- メンヘラ刑事 無料試し読み版 Righ…