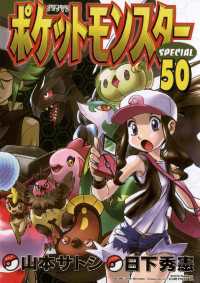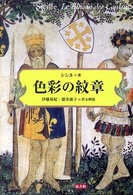内容説明
本書においてデリダは、『論理学研究』に見られる記号概念の分析を通じて、その模様を的確にあばきだすとともに、形而上学の囲いの踏み越えを示唆する。
目次
第1章 記号というものと諸記号
第2章 指標の還元
第3章 独語としての意義作用
第4章 意義作用とルプレザンタシオン
第5章 記号とまばたき
第6章 沈黙を守る声
第7章 根源の補欠
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel
5
この本の難解さは二つあって、一つは知覚に与えられる形相を言語の意義と直接結びつけるフッサール言語論の前提が納得しづらい点、そして形相を可能にする反復可能性の条件としてすでに文書を論じてたデリダがなぜ音声言語への閉じこもりに焦点を当てる必要があるのかである。後者は、そもそもフッサールに二つのベクトルがあり、知覚における言語の特殊性に焦点当てる側面と音声言語に閉じこもる側面があり、自身の目的から後者に充てるという大枠が出てくるのが遅いのが問題かなあと(一章終わり)。 2025/08/22
Bevel
4
目の前にあるものを括弧の中に入れるだけで、どうして確実性を保証する超越論的な領域の構成物を手に入れることができるのか。超越論的還元の操作の正当性をフッサールに信じさせた理由は何なのか。デリダはそこに「他我が存在しないから指標作用は存在しない」という想定、つまり「指標作用という媒介の消去」を見る。「私が私の声を聞く」として意識される私の声は、その表現が持つ指標作用と区別できず、結果、非現前性の痕跡を残す。最終的に、現前を通して存在だけが知られる非現前性は差延とされ、意識の可能条件は差延にとって代わられる。2012/09/15
む け
2
デリダの文章はやっぱり難しいと思うし、俺の読解力も足りてないと痛感させられる。フッサール現象学において指標作用とは別に意義性を持つ表現の層が仮定されているが、そこには伝統的形而上学の声(フォネー)中心主義がハあると、デリダは指摘する。声はエクリチュールとは違い自己の傍らに常にあり、かつ反復可能というイデア性をその性質に持つものだが、そもそも現前、自己触発においては必ず差延が存在するものであり、根源的な非現前性との差異が生じているのである。パロールからエクリチュールへ、大胆だなあと思ったけどやっぱり苦手…2013/02/10