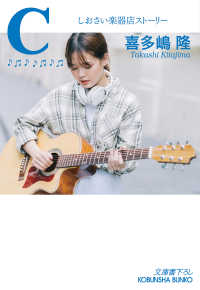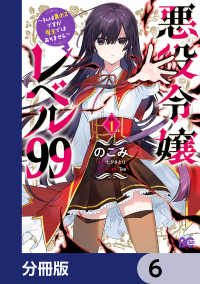出版社内容情報
平安時代に始まる京都の染織は、西陣織に友禅染が加わる江戸時代に頂点を迎えた。その後、明治の東京奠都で、一地方都市となった京都は、近代化の荒波の中でどのようにして危機を乗り越え〈染織の都〉たり得たのか。経営者、技術者・職人、画家たちの挑戦を通して近代染織業の歴史を辿り、「革新」が積み重なり「伝統」を形成していく姿を描く。
内容説明
平安時代から多彩な染織品を生み出してきた京都。近代化の荒波をいかに乗り越え“染織の都”たり得たのか。経営者、技術者・職人、画家たちの挑戦を通して歴史を辿り、「革新」の積み重ねが「伝統」を形成していく姿を描く。
目次
今を生きる京都染織品―プロローグ
“染織の都”誕生から開花へ 奈良時代~江戸時代
混乱する伝統と革新 明治維新期
期待される新しい染物と織物 明治一〇年代
機械織物か、美術織物か 明治二〇年代
国産化のススメ 明治三〇年代・四〇年代
台頭する京染と丹後ちりめん 大正期
流行をつくる百貨店と問屋 大正期
昭和恐慌と大衆ファッション 昭和初期
古都から産業都市“染織の都”へ 昭和戦前期
伝統と革新に挑戦しつづける―エピローグ
著者等紹介
北野裕子[キタノユウコ]
1958年、大阪府に生まれる。現在、龍谷大学・大阪樟蔭女子大学・京都女子大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
1
近代京都の染織業: 近代化 友禅染 西陣織 丹後ちりめん 化学染料 型友禅 機械化 捺染技術 技術革新と国産化: 図案研究 高等工芸学校 染料開発 国産化 技術移転 デザイン改革 織機改良 新素材導入 経済と市場動向: 内国勧業博覧会 明治宮殿装飾 洋装市場 輸出拡大 戦時統制 染織祭 観光振興 百貨店販売 教育と人材育成: 工芸学校 伝統技術継承 画壇の影響 技術者育成 若手支援 図案家 組合制度 技術交流 戦前・戦後: 昭和恐慌 七・七禁令 戦後復興 統制経済 染織業界組織 文化財保護 伝統と革新2025/03/02
takao
0
ふむ2025/07/29