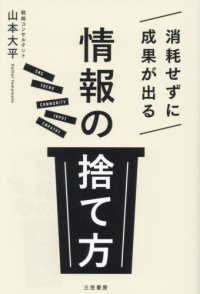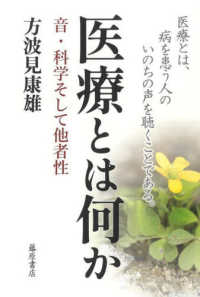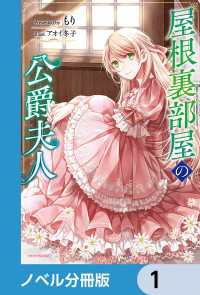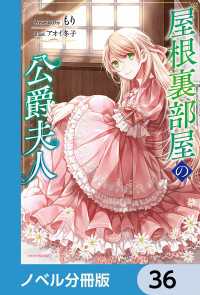出版社内容情報
日本の住まいは夏の暑さに合わせ開放的で風通しのよいものになったと言われるが、本当か。縄文の竪穴住居から近世の民家まで、祭礼や儀式、接客など、住まいがもつ社会的な機能とその変遷に着目。古民家の建築デザインの差異から「壁の空間」「柱の空間」という系譜を見出し、壁が少なく、ふすまや障子で部屋を仕切る日本固有の住まいの成立に迫る。
【目次】
序章 日本の住まいの特質
Ⅰ 寝殿造以前―「壁の空間」の住まい
第1章 竪穴住居と掘立柱建築
縄文時代の住まい
弥生時代の住まいと集落
古墳時代の豪族居館
家屋文鏡
家形埴輪
大王の館
継体天皇の系譜
第2章 奈良時代の宮殿と貴族住宅
律令制度の成立と都市・宮殿の建設
大化の改新と難波宮
飛鳥宮と藤原宮
奈良時代前期の平城宮
平城宮内裏から平安京内裏へ
奈良時代の貴族住宅
藤原豊成板殿
Ⅱ 寝殿造―「柱の空間」の住まいの誕生
第1章 寝殿造の成立
正月大饗
正月大饗の宴の二部構成
内裏の模倣
蔀の成立
第2章 寝殿造の空間構成
寝殿
渡殿と透渡殿
東対
中門・中門廊・西透廊
南庭
白砂・池
侍廊と外出居、台盤所廊
車宿と随身所
門と塀
西面の建物
第3章 寝殿造の儀式空間
幻の任摂政大饗
寝殿で行われた宴会
寝殿で行われた儀礼・対で行われた宴会
対での宴会
寝殿の儀式・対の儀式
対の平面の変化
儀式空間の装束
第4章 寝殿造の生活空間
『類聚雑要抄』室礼指図の立体図
『類聚雑要抄』の指図
柱間二間の生活空間
湯殿とトイレ
第5章 遣戸の発明と寝殿造の変化
紫宸殿
清涼殿の整備
清涼殿における遣戸の成立
遣戸の普及
儀式用の住まいと居住用の住まい
白河上皇の六条殿
平清盛の六波羅泉殿:居住用の屋敷の特徴
総柱建物
九条兼実の冷泉富万里小路邸:総柱建物と任大臣大饗
近衛殿指図
東三条殿の焼失と最後の正月大饗
Ⅲ 書院造―「柱の空間」の住まいの完成
第1章 寝殿造から書院造へ
慕帰絵詞
母屋・庇から「間」へ
床の間(押板)・違棚・付書院
上段
帳台構
第2章 鎌倉・室町幕府の空間と儀式
鎌倉幕府の空間
大倉御所の焼失とその後の鎌倉将軍邸
室町幕府の正月儀礼
義満以前の室町将軍邸
義満の室町殿
北山殿と金閣
北山殿行幸
第3章 会所と対面所
公卿座から会所へ
室町将軍邸の東面と西面
義教邸の対面空間
義教の室町殿
会所とは何か
義政の烏丸殿と室町殿
義政の東山殿
第4章 近世武家住宅の成立
大坂城と聚楽第
千利休と待庵
家康によ
内容説明
日本の住まいは蒸し暑い夏に適応するように作られたものではない。竪穴住居から古民家まで、空間のもつ機能やデザインの違いに着目。壁が少なく、ふすまや障子で部屋を仕切る開放的な住まいが形成された歴史を解明する。
目次
序章 日本の住まいの特質
1 寝殿造以前―「壁の空間」の住まい
2 寝殿造―「柱の空間」の住まいの誕生
3 書院造―「柱の空間」の住まいの完成
4 民家―日本の住まいの集大成
終章 世界から見た日本の住まい
著者等紹介
川本重雄[カワモトシゲオ]
1953年、岐阜県に生まれる。1982年、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了(工学博士)。元、京都女子大学学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HMax
みさと
Go Extreme