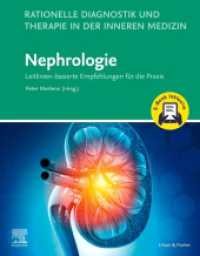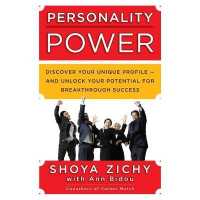出版社内容情報
明治5年、湯島聖堂博覧会開催を機に誕生した東京国立博物館。初期収蔵品や明治期の展示風景、関東大震災、第二次世界大戦などの難局をどのように乗り越えたか、話題を呼んだ展覧会など豊富なトピックと写真で150年のあゆみ、現在の活動の舞台裏や展示施設の特色を紹介。文化財を守り伝えることの大切さを感じながら博物館の魅力に迫ります。
内容説明
日本・東洋の文化財の宝庫、東京国立博物館の歴史といまを徹底解剖!創立150年、日本最大の博物館をより深く楽しむためのガイド。
目次
写真でたどる東京国立博物館の歴史(明治;大正;昭和;平成)
東京国立博物館のいま(独立行政法人化以降の特別展―日本の美術から世界の美術まで;教科書で見たあの作品に出会える!―東京国立博物館の収蔵品)
東京国立博物館 館内めぐり(本館;東洋館;表慶館;法隆寺宝物館;平成館;黒田記念館;構内マップ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シフォン
31
昨年、会期延長で何とか鑑賞することができた国宝展、本館の建物はいつ見ても風格のある佇まい。東洋館は正倉院をイメージした谷口吉郎の設計、法隆寺宝物館は息子の谷口吉生の設計、東洋館では、東洋の仏教美術の収蔵品の多さに驚き、法隆寺宝物館では、飛鳥時代や平安時代の品々が今でも存在していることに驚く。博物館の使命は、文化財の収集保管、展示公開、調査研究、日本文化の継承と発展に寄与すること。ゆっくり見たい。「くちなわ物語」の昭和初期の文化財の輸送や正倉院御物特別展やモナリザが来日したときの行列の絵など面白い。2023/03/06
きゅー
6
今年2022年は東京国立博物館の創立150周年となっている。その150年の歴史を簡単にまとめたものが本書。写真が多用されビジュアル重視。今おこなれているイベントに連動して、軽く歴史をおさらいしたい場合にはちょうど良いかも。内容の量としては、トーハクのHPをじっくり見たほうが多そう。2022/12/06
ユウティ
4
ぱらぱらと。博物館の歴史9割、最後に館内紹介といった感じ。ちょうど池を埋めて芝にしてイベントを実施すると話題なので、池っていつからあったんだろうと思いながらざっと読む。(個人的に芝はありかもだけど、櫓?とイベントはどうかなあ)池は今の場所に建ったときには形は違うがもうある。関東大震災で玄関崩落からの取り壊し→現在の建物に建て替え直後は前庭が見える写真がなくて結局分からなかった。HPは敷地内の施設の情報がぶつ切れで、常連さんじゃないと分かりにくい感じだったので、中を歩いて回る紹介本があればまた読みたい。2025/11/12
氷菓子
4
明治期の博覧会に出品された作品の寄贈や、公家、武家の旧蔵品を購入したものを収蔵したところから始まる。上野動物園も元は博物館の付属施設。関東大震災で国立科学博物館の前身の東京博物館が展示資料を失ったので、東京国立博物館は所蔵していた自然史資料9万点を譲渡し、それ以降は歴史・美術を中心とするようになった。本館入口は博物館・美術館の地図記号のモデルらしい。常設の他に、様々な特別展が開催されているが、過去最高の入場者数は昭和49年のモナ・リザ展の150万人。2022/11/26
やま
3
トーハクもしばらく行けていない。東京にいきたいな。2024/07/06