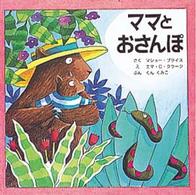内容説明
中世まで無頓着に扱われた子どもが、江戸時代の半ばから大切に保護されるようになったのはなぜか。また、民俗学の通説「七歳までは神のうち」が、伝統的心性とは全く無縁であることを実証。これまでの幼児観を見直す。
目次
新たな幼児観をさぐる
法のなかの幼児(疎外される幼児;近世服忌令と幼児;服忌令と明律の浸透)
疎外から保護へ(古代・中世の幼児;幼児保護観念の成立;保護される捨子;俗説“七つ前は神のうち”の成立)
幼児観はなぜ変わったのか
著者等紹介
柴田純[シバタジュン]
1947年、愛知県に生まれる。1972年、京都大学文学部国史学科卒業。1981年、京都大学大学院博士課程国史学専攻単位取得満期退学。現在、京都女子大学文学部教授、京都大学博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しろきいろ
1
図書館。生物として子を愛着する個々の話ではなくて昔に世間様が乳幼児をどう扱ってたかという関係を検証した本。七つまでは神のうちってフレーズが定着したことでまともに検証されてこなかった中世からの幼児観を具体的な史料をもとに再検証してくのですが、ときどき怪異譚みたいなおもしろエピソードがでてくる。2016/02/20
鵜殿篤
0
【感想】教育学研究者としては、「七つ前は神の内」というキャッチフレーズが、実は日本人の伝統的心性となんの関係もなく、近代以降に形成されたただの俗説だという説明に、かなり安心した。授業でアリエスなどを扱う際に日本の話に及ぶとき、この「七つ前は神の内」という言葉のせいで整合性が失われてしまうような違和感があったからだ。2017/04/18
さんた
0
大権威の発言で後の人たちが思考停止になったようなもんか。 いくら大権威の発言だろうと、実例をあげたり、他人が実証検証できないものを真実扱いしてはいけないと思うが、しがらみの中では無理なのか。2013/05/18
-

- 電子書籍
- 妖精が導く復讐と願いの交差点【タテヨミ…