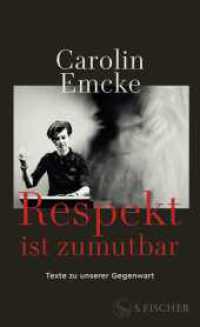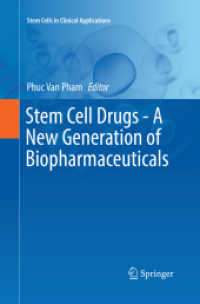出版社内容情報
★読売・日本経済・産経・山形新聞各紙で紹介されました!
内容説明
都の景観や風俗が描かれた洛中洛外図屏風。そこには戦国の京都に生きた権力者たちの姿が、生き生きと描かれていた。誰が、何のために描かせたのか。屏風製作の背景や時代の様相を探り、読者を謎解きの世界へと誘う。
目次
初期洛中洛外図屏風とはどんな絵画か
1 歴博甲本を読む(登場人物をさぐる―幕府・細川邸など;描かれた武家と公家の屋敷;細川高国の事績と作者;伝来について;都市民衆の世界―床屋と両側町;洛中洛外図屏風『朝倉本』に描かれたもの)
2 東博模本を読む(東博模本の背景;描かれた細川邸と幕府;東博模本の制作事情)
3 上杉本を読む(上杉本の成立事情;上杉本の中心主題;洛中洛外図屏風としての特質;都市の風俗と季節)
4 歴博乙本そしてその後(歴博乙本の特色;洛中洛外図屏風のその後)
著者等紹介
小島道裕[コジマミチヒロ]
1956年横浜市生まれ。京都大学文学部卒業、同大学院博士課程単位取得、博士(文学)。現在、国立歴史民俗博物館/総合研究大学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジャズクラ本
15
○吉川弘文館の本だけあって読み応え充分。洛中洛外図屏風の中でも初期の朝倉本(現存せず)、歴博甲本、東博模本、上杉本、歴博乙本を解説解読しているのだが、論文といっても過言ではなく、屏風に描かれた人物の特定まで行われている。この点、ついていけないところは適度に読み飛ばした。僕のこの屏風に対する興味は当時の風俗なのだが、初期のものは権力者を主題としており、風俗主題で描かれるのは歴博乙本以降だそうである。従い、この本も風俗の観点での記述は少なく、この点では残念だった。折をみて風俗主体のものをまた読んでみたい。2020/12/13
あや
10
室町時代に描かれた洛中洛外図である『歴博甲本』『東博模本』『上杉本』『歴博乙本』に関する歴史的背景や人々の暮らしぶりが書かれていて非常に面白く読めました。この四作の中でも特に有名な上杉本に関する話が一番印象的でした。歴博甲本は自らの構想が実現しつつあることを誇って書かれたものであるが、上杉本は自らの理想が実現できないと悟り、それ自体を受け入れがたく現実逃避に走って書かせた屏風である。それを知り色彩豊かな絵にも関わらず、何だか悲しい作品に見えるようになりました。機会があればぜひ実物を見に行きたいものです。2013/02/04
千尋
7
戦国時代の京都が描かれている洛中洛外図屏風についての研究書*この本では、「歴博甲本」、「東博模本」、「上杉本」、「歴博乙本」など・・様々な洛中洛外図屏風の検証がされていて、誰が何のために描かせたのかとか図屏風の特色が詳しく書かれています*特に「上杉本」は将軍・足利義輝が上杉謙信の上洛を夢見て描かせた図屏風で、上杉謙信が描かれていてとても印象に残りました**2010/11/06
アメヲトコ
2
いわゆる初期洛中洛外図屏風の読解を試みた本。幻の「朝倉本」の構図など、かなり大胆な推論を行っている章もありますが、本書の中心をなす歴博甲本の読み解きは、政治動向を視野に入れながら事物を丹念に分析して立論されており、説得力があります。図版も豊富で、また巻末の参考文献は単なる書名の羅列でなく紹介文付きでとても良心的。2014/08/18
うみ
0
読み終わったところで,れきはくに洛中洛外図屏風を観に行く!!2012/05/05