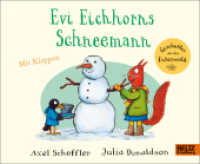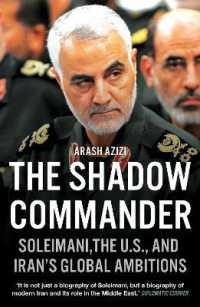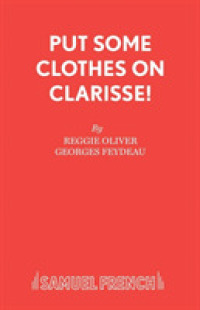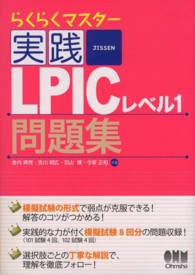出版社内容情報
5世紀後半から6世紀前半に実在した継体天皇は応神天皇五世孫なのか、王統とはつながらない地方豪族であったのか。なぜ即位後20年間大和入りを果たせなかったのか。出自をめぐる問題、擁立勢力と即位の事情などを、真の陵墓といわれる今城塚古墳の発掘成果や近江の古代豪族息長氏との関わりを交えて解明。謎に包まれた継体天皇の実像を探る。
内容説明
継体天皇は応神天皇五世孫なのか、王統とはつながらない地方豪族であったのか。出自をめぐる問題、擁立勢力と即位の事情などを、今城塚古墳の発掘成果や息長氏との関わりを交えて解明。謎に包まれた実像を探る。
目次
1 継体天皇の出現―日継知らす可き王無し
2 継体天皇と近江・越前―三尾氏と三国氏をめぐって
3 継体朝の成立と息長氏
4 継体朝成立前夜の政治過程―和迩氏と息長氏の動向を中心に
5 継体天皇のヤマト進出
6 継体朝は新しい王朝か―研究の歩み
著者等紹介
大橋信弥[オオハシノブヤ]
1945年茨城県石岡市に生まれる。1972年立命館大学大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了。現在、滋賀県立安土城考古博物館学芸課長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
38
どうやら著者は継体天皇から新王朝になったと主張したいようだが、もともと資料の少ない日本古代史で戦後の悪弊である「記紀」の否定を行っているので、残された道は仮説という名の推測という方法しかとれなくなる。何ら論証することなく、継体は「即位後ただちに大和の中枢部には入れず」としているが、「入らず」の可能性については何の検討もしていないのだ。育った土地が水上交通の盛んな滋賀とも福井とも言われる継体天皇が山に囲まれた大和に行くことが安心できると考えていたとは到底考えられない。抵抗勢力となった豪族は特定すべきだろう。2024/06/10
Makoto Yamamoto
9
継体天皇には出身、今住んでいる県がかかわっているので興味があった。著者の過去の論文、発表文章を使っているらしく、同じ文章が何度も出てくるのにはまいった。 上宮紀という書物に応神天皇から継体天皇までの系図があるというのは興味深興味深かった。 その系図を高槻市の今城考古博物館で確認できて、納得した。 もう少し整理してから出版してほしかったのが本音。2019/10/08
wang
2
謎の多い継体天皇の妃后の出身氏族などから継体の権力基盤がどこにあったのかを特定し、出身氏族や勢力関係そして当時の天皇家との関わりの謎に迫っている。またそれら氏族が天武朝でどのように扱われたかなど後の世でどう評価されているかで継体朝との関わりを推理する点などは説得力がある。ただバラバラに発表された論説を集めただけなので同じ記述が何カ所にもあり読みにくい。きちんと抜粋整理して出版してほしかった。2012/08/01
ヨシモト@更新の度にナイスつけるの止めてね
1
継体天皇ことヲホドノミコトの出自、婚姻、勢力、次代へのバトンタッチなどの謎を、記紀などの文書、出土品、地名、伝承などを総合的に分析する。少し前から彼に関する定説は変化を見せているようで、これからも多くの学者がワァワァ言いながら検討してゆくのだろう。記紀を読んでいる最中にちょっとでもアレ?とひっかかるような箇所には、やはり多くのトラップが仕込まれているということだ。そう考えると、雄略天皇に世継ぎの男子がいなかったということ自体が、非常に不自然だなと思えてくる。この本、2020年に新装版が出たことが喜ばしい。2020/06/09