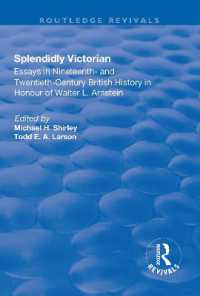内容説明
江戸時代、民衆とともに生きる修行僧がいた。米穀を断つ木食僧、仏像を刻む聖、加持祈祷をする修験者。彼らはなぜ諸国を漂泊し、苦行に身を投じたのか。民衆に支持された民間宗教者の足跡から、日本宗教史の深層に迫る。
目次
漂泊する聖たち―木食・修験・陰陽師
1 江戸前期の木食僧(弾誓上人―岩窟の中の聖者;風外慧薫―草衣の禅僧;円空―鉈切仏の聖 ほか)
2 江戸中後期の木食僧(木食観海;木食仏海;木喰行道―微笑仏の聖 ほか)
3 六十六部・修験・陰陽師(お廻国様;独信行者―箱根山中の山岳修験者;陰陽師―指田摂津藤詮の旅 ほか)
民間宗教者の意味―エピローグ
著者等紹介
西海賢二[ニシガイケンジ]
1951年神奈川県生まれ。1984年筑波大学大学院歴史人類学研究科博士課程修了、博士(民俗学)。東京家政学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 目でみる女性スポーツ白書