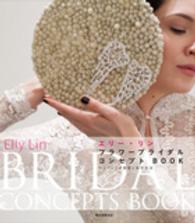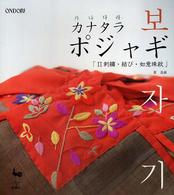内容説明
古代から現代まで、戦争のあり方や戦争をささえたシステムを明らかにする通史。戦争遂行のための“人と物”の調達をキーワードに、軍事に関する制度と、軍隊と社会の関係を多くの写真や絵画とともにビジュアルに描く。
目次
古代・中世(戦争の始まり―弥生時代から古墳時代;「東夷の小帝国」の軍隊―奈良時代から平安時代初期 ほか)
戦国時代(戦国動乱の展開;臨戦体制の確立 ほか)
近世(戦乱の終結と幕藩体制の確立―十七‐十八世紀;北方紛争と海防体制―十八世紀末‐十九世紀初期 ほか)
近代(外征軍隊としての「国民軍」建設―一八七二-一八九四;日清・日露戦争―一八九四‐一九〇五 ほか)
戦後(冷戦下の再軍備―敗戦‐一九七〇年代;対米追従か、国際貢献か―一九八〇年代‐現在)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Jampoo
11
弥生時代から現代まで、日本の軍事についての網羅的な通史。 微視的な戦術や武器の技術革新だけではなく、政治体制や権力構造まで詳しく書かれており、軍制のシステムから兵卒の価値基準までが社会状況と表裏一体なのだという事を強く感じた。 天武天皇の時代に大宝律令の下で作ろうとした中央集権的な軍団は中世史の感覚では非常に先進的で驚いた。 9世紀には軍団制の廃止やそれに関わる官司の統廃合が進み、国司のイエが独自に抱える軍事力から武士の台頭へと繋がる。 源平合戦や大阪の陣の要因を地方領主や浪人の視点から語る所も面白い。2025/08/12
ryooyr
3
読みやすくてよくまとまっていた。戊辰戦争時の新政府軍の苦しすぎる収支や、戦国時代の陣夫システムあたりが特に興味深かった2012/05/19
たぬき
2
一つの軸でビシッと2011/07/02
やご
1
題字のゴツさと400ページ超の分量についビビってしまいそうですが、あくまで一般向けの概説書なので読みやすいです。日本の軍事制度を古代から現代に至るまで追ったものです。非常に長い時代範囲を対象としているため、400ページ超あっても足りるのかなと読み始めるときはちょっと疑問だったのですが、要点をうまく絞ってよくまとめています。良書。2006/08/07