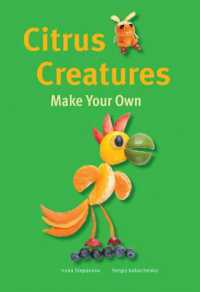出版社内容情報
特別なハレの日の食とされる餅は、私たちの生活にいかに関わっているのか。全国の事例を調査し、そこから見える民俗・文化に迫る。
内容説明
正月の雑煮など、日本人にとって特別なハレの日の食とされる餅。だが、中には正月に餅を食べない地方も存在する。餅は私たちの生活にどのように関わっているのか。全国の事例を調査し、そこから見える民俗・文化に迫る。
目次
序論 民俗学者が餅の向こうにみたもの―柳田国男と坪井洋文
1 餅正月をめぐって(民俗世界における餅の意義―その社会性に注目して;雑煮の意味―家風と女性;モノツクリの象徴―米から金へ)
2 餅なし正月をめぐって(餅なし正月の解明―複合と単一の視点から;流行神と餅なし正月―餅なし正月の多面性1;家例からみた餅なし正月―餅なし正月の多面性2;作物禁忌からみた餅なし正月―餅なし正月の多面性3)
著者等紹介
安室知[ヤスムロサトル]
1959年東京都生まれ。筑波大学大学院環境科学研究科修了。熊本大学文学部助教授、国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授を経て、神奈川大学国際日本学部教授、日本常民文化研究所所長、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちり
2
“時代をさかのぼると、これまで共通すると考えられてきたこと、たとえば雑煮が食されるのは正月であるというのは明らかに間違いであること、さらに雑煮という名称そのものが全国共通ではないことが明らかとなる/雑煮の場合、じつは時代差が大きく作用し、雑煮が記録された時代によって地域差の様相は異なってくる/雑煮の地域差は特に東西差は、コマーシャリズムとマスメディアにより増幅された感がある。そこに時代差の考えはなく、地域ごとの特徴(地域性)は固定的で昔から続くものという前提がある”2021/02/07
takao
2
ふむ2021/01/20
Humbaba
1
かつては資産とは家の持ち物であり、個人のものという意識は薄かった。しかし、そのような時代にあってもお年玉という形で餅を個人に対して渡しており、その餅はあくまでもその人個人の持ち物であった。それだけ餅というものは大切な意味を持っており、他のものとは違った価値があった。現在ではそのような意識はなくなってしまったが、だからこそその当時の考えを知り風習を理解するということは大切であろう。2025/03/23
いち
1
ハレのもち。2022/01/22