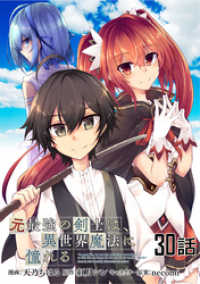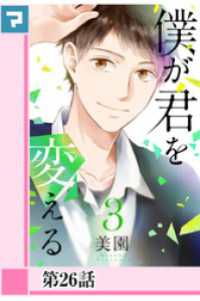出版社内容情報
蒙古襲来、鎌倉幕府滅亡、南北朝内乱と、動乱の渦に東海も巻き込まれていく。三河を地盤に覇権を握った足利氏のほか、北畠・土岐・今川氏とその支配地域の動向を詳述。東海一帯に影響力を及ぼした寺社勢力にも説き及ぶ。
内容説明
蒙古襲来、鎌倉幕府滅亡、南北朝内乱と、動乱の渦に東海も巻き込まれていく。三河を地盤に覇権を握った足利氏のほか、北畠・土岐・今川氏とその支配地域の動向を詳述。東海一帯に影響力を及ぼした寺社勢力にも説き及ぶ。
目次
序 鎌倉後期~南北朝期の東海―東海中世史への招待(谷口雄太)
1 足利氏と三河地域(谷口雄太)
2 伊勢地域と北畠氏(大藪海)
3 土岐氏と濃尾地域(山田徹)
4 駿遠地域と今川氏(堀川康史)
5 東海地域と顕密仏教―三宝院流の展開を中心に(小池勝也)
6 東海地域と禅宗(斎藤夏来)
著者等紹介
谷口雄太[タニグチユウタ]
1984年、兵庫県に生まれる。現在、青山学院大学文学部准教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
7
南北朝期だけで1巻に仕上げているのが面白い切り口。三河の吉良氏、駿遠の今川氏、美濃の土岐氏、伊勢の北畠氏が大きく扱われている。京と関東の連絡路確保が重要だった南北朝の争乱で、足利一門と源氏一門が東海道に根を張ったことは、北朝の優位を確保する上で重要なことであったと思う。北畠のみ南朝方で毛色が異なるが、劣勢の中でも粘り強く継戦を続けたことが、戦国時代末期まで伊勢南部で勢力を保てた要因であろう。また三河武士というと徳川ばかりが有名だが、足利一門の拠点も三河であった。南北朝期も三河武士が列島を翔けたのだ。2024/08/18
吃逆堂
2
南北朝期の東海地域を考える際に、足利一門の動向はたしかに重要であろうが、地域史の一般書として足利一門を中心にすえていいのだろうか、というタイトルを見たときの違和感が読んでも今ひとつ消えなかった。結局、武家領主でとりあげている半分は、足利一門ではない氏族だし。 《特定地域における特定氏族の歴史》と《特定氏族の展開にかかわる特定地域の歴史》というのは、似ているようで別物であって、慎重にきりわけなければいけないのではなかろうか。2024/09/11