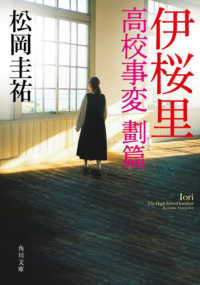出版社内容情報
江戸時代の多彩な文化は、人びとの生活や思想にいかに反映されたのか。寺社・学問・医療・旅・文芸・出版物などをめぐる新たな潮流を生み出し、受けいれた社会に光をあて、身分と地域を超えた人びとの営みを描く。
内容説明
江戸時代の多彩な文化は、人びとの生活や思想にいかに反映されたのか。寺社・学問・医療・旅・文芸・出版物などをめぐる新たな潮流を生み出し、受けいれた社会に光をあて、身分と地域を超えた人びとの営みを描く。
目次
プロローグ 多彩な文化をみる視角(小林准士)
第1章 近世的な政教関係の形成(林晃弘)
第2章 仏教教団・宗派の構造(朴澤直秀)
第3章 民間宗教者の活動と神社(梅田千尋)
第4章 学問流派の分立と教育・教化(小林准士)
第5章 民衆の生活における思想・信仰(上野大輔)
第6章 民間社会からみる書物文化と医療の実態(鍛治宏介)
第7章 近世の寺社参詣とその社会的影響(原淳一郎)
著者等紹介
上野大輔[ウエノダイスケ]
1983年、山口県に生まれる。現在、慶應義塾大学文学部准教授
小林准士[コバヤシジュンジ]
1969年、岐阜県に生まれる。現在、島根大学法文学部教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
10
江戸時代の文化史はよく知らないのでお勉強だと思って読む。7章の内4章が宗教関連の話題で、知識不足もあって興味深いけど面白いまでは至らずという感じ。寺院への統制はかっちりしたヒエラルキーの下で行われていたけど、神道関連はゆるゆる体制だったというのは「へー」って思った。確かに教科書だと寺請制度や宗門改めなどお寺は行政に組み込まれているけど、神道は思想しか取り上げられないもんね。あと江戸時代の識字率は世界一という与太話の流布に司馬遼太郎が絡んでいるのが、一番印象に残った部分だったりする。ここにもあるか司馬史観。2025/09/23
アメヲトコ
5
2023年10月刊。近世の多様な文化について取り上げた巻です。プロローグでは「重層と複合」論を引いて諸身分間の競合と棲み分けを論じていますが、その点では第2章の市屋道場金光寺をめぐる諸関係の分析や、第4章の学問の担い手の横断的な分析などは興味深かったです。2024/10/21
はるたろうQQ
1
近世文化史全般に渡る総合的見地を獲得することを目指すと言うが、羊頭狗肉なのは仕方ない。各々の論文は面白い。2章、3章を読むと色々な立場を使い分ける宗教者が出て来くる。4章でも医が仏や儒から分化独立していく様子が記される。識字率に関し司馬遼太郎をディスる記載があるが、この章は村の蔵書内容を明らかにするもので、春画のコラムや7章の精緻な旅のシステムと西国巡礼や四国遍路に赴いた山形の女性のこと等を考えると、司馬の言説に飛び付きたくなる。文書資料を読み解くことを第一とする歴史学自体への自戒の文章でもあるのだろう。2025/11/20
-

- 洋書
- ENTRE ELLES