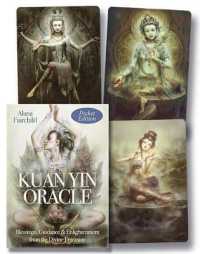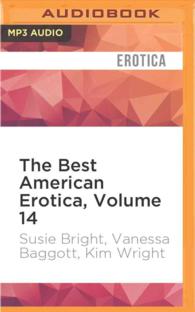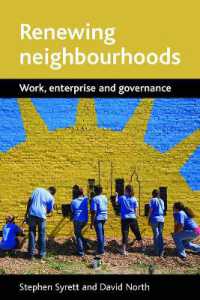出版社内容情報
16世紀前半、明応の政変などを経て室町幕府は分裂。分権化が進み、新たな社会秩序の形成へと向かう。三好政権の成立、山城の発展、京都や大阪湾を取り巻く流通などを描き、畿内近国における争乱の歴史的意味を考える。
内容説明
十六世紀前半、明応の政変などを経て室町幕府は分裂。分権化が進み、新たな社会秩序の形成へと向かう。三好政権の成立、山城の発展、京都や大阪湾を取り巻く流通などを描き、畿内近国における争乱の歴史的意味を考える。
目次
将軍の更迭・追放・殺害の反動―プロローグ
1 将軍家・管領家の分裂
2 三好政権の成立
3 畿内社会の様相
4 宗教と文化
5 領国の支配
6 相対化される幕府
統一政権の前提―エピローグ
著者等紹介
天野忠幸[アマノタダユキ]
1976年、兵庫県神戸市に生まれる。2007年、大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程修了。現在、天理大学文学部准教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
14
三好氏の研究者として知られる著者だが、畿内の戦国期社会を広く題材として、足利義稙から義昭期までを描く。著者の説く将軍(または将軍候補)を推戴しない三好氏の権力の在り方など、これまでの著者をはじめとする諸研究を手際よくまとめる。文化史の題材にも紙幅を割いてをり、示唆に富む。 2020/11/23
MUNEKAZ
14
永正の錯乱から足利義昭政権の成立まで。概説書らしく著者の三好贔屓も落ち着き気味で、有力寺社や村落、有徳人の動向もバランスよく描かれている(相変わらず足利義輝に対する評価は厳しいが…)。両細川の争いに畠山家の内訌、そして義澄流・義稙流の将軍家分裂と、カオス極まる畿内情勢を、自身が頂点に立って新興の領主たちを従えることで止揚させた三好長慶の画期性はやはり凄い。あえてどの派閥にも属さないことで、争いの連鎖を断ち切ったというところか。畿内の戦国時代の最新研究を、俯瞰して眺められる良い本ではないかと思う。2020/08/09
フランソワーズ
6
明応の政変以後、三好政権とその没落までの通史。三好氏研究の第一人者らしく、同氏についての論述はさすがです。幾筋にも錯綜する関係人物はやはりわかりにくく、それが地方の戦国大名と比べて人気がない一因かと。そんな複雑な政治史とは別に、第3・4・5章は概説書の割に充実していてよかったです。2024/12/08
mallio
2
政治や軍事だけじゃなくて、経済や文化も網羅されていて、応仁の乱以降信長登場までの畿内を中心とした動きがよくわかります。途中で、各大名家の個別事例に触れていて、最後に畿内で総まとめのようになっており、それぞれの出来事が複雑に繋がっているんだよな・・・と改めて思いました。2020/08/20
Junk
1
取り上げられることが少ない室町幕府の後期の畿内を中心とした動向を知ることができた。 応仁の乱後、足利は衰退していき、細川、六角、三好などの勢力が次々と権力を掌握し、衰退するのを繰り返し、その過程で権力の掌握の方法が変化していき、それが幕府の消滅に繋がったのと理解できた。 また信長の時代には衰退していた守護大名が室町後期にどういう役割を果たしていたのかも知ることができた2024/06/08