内容説明
私たちの生活に欠かせないハンコ(印章)。メソポタミアを発祥の地とし、西はギリシャ、東はインダス・中国、そして日本へと伝わった。各地域・時代における形態や使われ方から、ハンコと人間の関わりを探る。
目次
第1章 ハンコの誕生(文字よりも古いハンコ;ハンコは鍵の代用;粘土からパピルスへ;ハンコが語る古代貿易ルート)
第2章 ヨーロッパに渡ったハンコ(ハンコのるつぼ―クレタ島;絵が中心のギリシャ・ローマ印;中世のハンコ;印章・紋章・署名)
第3章 ハンコの東漸(中国印の起源;身分の証明;ひろがったハンコの用途;金より高価な印材)
第4章 ハンコロードの終着駅・日本(失われた金印;律令制度がもたらしたハンコ;戦国武将の印判状;ハンコなしでは夜も日も明けぬ国)
第5章 糸印の謎を解く(糸印とはなにか;糸印のルーツを探る;勘合貿易と糸印;糸印と根つけ)
著者等紹介
新関欽哉[ニイゼキキンヤ]
1916年東京生まれ。1938年東京大学法学部政治学科卒業。外務省大臣官房情報文化局局長、駐ソ大使、原子力委員、日本国際問題研究所所長を歴任。2003年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
26
ハンコは鍵の代用(13頁~)。わが国最初の蔵書印は金沢文庫(123頁~)。サインが通用する文化と、未だにハンコの日本のやり方と、どちらがいいのかと思う。パスワードとしてのハンコという時代もあったようなので、セキュリティばかり目が行くのだが、認め印という意味が大きいと思う。2015/08/23
スプリント
7
オリエントから西欧・東洋へハンコ文化が伝搬し独自に発展した地域もあれば廃れてしまった地域もあることがわかります。後半の糸印の秘密も読み応えがありました。2015/07/10
さとうしん
4
オリエント・西欧・中国・日本と世界各地のハンコ文化について総覧しているが、中国のハンコが鉄器・金属貨幣の使用とともにオリエントから伝来したとしている点が注目される。本書で紹介されている殷鉨については、近年近年考古発掘による出土例が紹介されていたと思うが。2015/07/10
tacacuro
2
世界で初めてハンコを使ったのはシュメール人で、それがギリシャ・ローマを通じてヨーロッパへ、さらに西から中国に伝わり、遣隋使を通じて日本でも使用されるようになったという。一般民衆にまで広がったのは江戸時代で、明治時代に自署かハンコかという大論争があり、大蔵省や金融界を中心とする自署主義への大反対論に押されて、記名捺印によって署名に代えられる法律ができたと。江戸時代にどのように一般民衆に広まったのか、もう少し詳しく知りたくなった。2021/02/14
saba
1
ハンコ=印章の起源はオリエントだが、ヨーロッパではその意匠的な部分は紋章に受け継がれ、契約を証する意味合いはサイン(signの語源はラテン語の「印章」!)へと変遷。一方の東洋では、絵を彫り入れることはなくなっていき印章の表面においては様々な字形で字のみを彫るようになった。「漢字」という極めてビジュアル的な表意文字であるからこその変化がドラマチックでしびれる。著者は外交の第一線で活躍されたかただそうで、中盤の中国の石語りが激熱だったがやはりそこが発端らしい。バビロンの石板の逸話に萌えた。2020/12/09
-
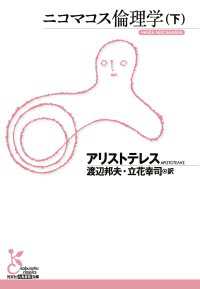
- 電子書籍
- ニコマコス倫理学(下) 光文社古典新訳…







