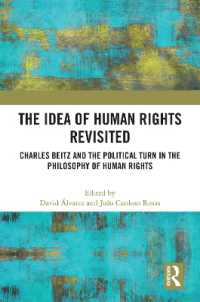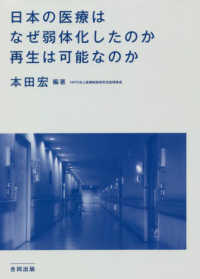内容説明
近江の土豪から頭角をあらわし、信長・秀吉のもとで才能を発揮。徳川・毛利に次ぐ広大な領地を有する大大名にいたるも急逝した氏郷の生涯を辿る。キリシタン大名、利休七哲としての交友や、伊達政宗との関係も検証。
目次
蒲生の系譜(蒲生の稲置;非御家人 ほか)
日野六万石(新しい波;氏郷初陣 ほか)
松坂少将(峯の戦い;南北転戦譜 ほか)
りはつ人(風雅の道;猛き心 ほか)
会津移封(小田原の夜討ち;会津入り ほか)
領国の経営(会津若松城;会津九十一万石 ほか)
著者等紹介
今村義孝[イマムラヨシタカ]
1908年熊本県飽託郡島崎村に生まれる。1930年東京高等師範学校卒業。高田師範学校教諭、熊本県立天草中学校教諭、秋田師範学校教諭を経て、1949年秋田大学助教授。1952年同教授(1973年退官)。2006年帰天(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
21
市民大学院の諸先生方から学んだことがきっかけで借りてみた。がもううじさと。1967年初出。当代歌壇の代表的人物に学んで、氏郷は素心をみたし、風雅の道を深めた(128頁)。氏郷も茶器を愛し、双月の葉茶つぼ、長次郎作鉢開き、鍋屋肩衝(かたつき)の名が知られている(134頁)。 氏郷は東北の押えとしての使命を果たすとともに、広大な領国の軍事・経済的封建支配の中心としての城郭と城下町の建設を考えた(202頁)。氏郷は40歳で亡くなった。2015/06/23
こけしだ
7
近江日野で生まれ、信長・秀吉のもとで武功をあげ、のちに会津へ移封となった後は黒川城を改め会津若松城を築城し城下町を整備した。利休とも信頼関係を築いていたそう。利休の次男を会津でかくまい千家の再興に力を尽くす。以前「優れた武将ゆえに秀吉から警戒され会津へ移封となった」と紹介されているのを見たことがあったが、この本ではあくまで秀吉が会津を奥州支配の要と考え、油断ならぬ伊達政宗を抑えるためにも氏郷に任せたとのこと。伊達政宗との関係は穏やかではなかった模様。俄然伊達政宗にも興味が湧いちゃう。2021/04/09
Kiyoshi Utsugi
4
蒲生氏郷の生涯を辿ったものです。 織田信長、豊臣秀吉に仕え、中野城(近江国)→松ヶ嶋城(伊勢国)→松坂城(伊勢国)→黒川城(陸奥国)と居城を替え、最終的にはほぼ92万石を領国とする徳川、毛利に次ぐ大大名になっています。 黒川城は今の会津若松城で、黒川を若松と改めたのも蒲生氏郷のようです。 残念なことに40歳の若さで亡くなって、京都の大徳寺の昌林院(現在は黄梅院)に埋葬されたとのことです。 遺髪は会津の興徳寺に埋葬されたとのことです。 このうち、黄梅院には行ったことがないので、行ってみたくなりました。2019/10/12
-
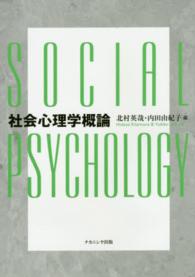
- 和書
- 社会心理学概論