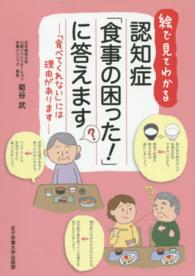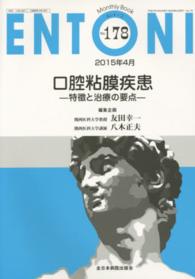内容説明
日本全国に広く分布する。建物はおろか石垣も水堀もない中世の“土の城”。永年の縄張研究の成果を原点から見つめなおし、それらが形成する地域の特徴をとらえ、軍事的・社会的段階の変化、近世への道のりをたどる。
目次
1 山形県最上地域へ(志茂の手館;空間その1―最上盆地;空間その2―最上地域)
2 宮城県伊具地域へ(冥護山館・陣林館;遠倉館・前田館―「村の城」;空間―伊具地域 ほか)
3 岡山県総社地域へ(経山城;幸山城・福山城;空間その1―備中国府域;空間その2―総社地域)
4 広島県三次地域へ(南山城・鳶巣山城―「土塁囲みの小郭」;ハチガ檀城;空間―三次地域)
5 埼玉県比企地域へ(杉山城;陣の遺構をさぐる;織豊系「陣城」とは似ているか;空間―比企地域)
6 空間と時間(大名と地域;技術体系;火点の構成技法;「比企型虎口」のゆくえ;平井金山城の意味するもの)
著者等紹介
松岡進[マツオカススム]
1959年、東京都に生まれる。1982年、早稲田大学第一文学部卒業。2003年、早稲田大学より博士(文学)の学位を授与される。現在、東京都立桜町高等学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kiyoshi Utsugi
30
先日読んだ中井均氏と齋藤慎一氏の本の中にも参考文献としてあがっていたもので、早速図書館で借りて読んでみました。他の本より優先度をあげて…😅 今頃気がついたのですが、これまで何度も読んで掲載されてるお城をコンプまでしてた「神奈川中世城郭図鑑」の共著者の一人でした。著者の紹介では、高校の先生となっていたので、あまり注目してなかったのですが、博士号まで持った研究者で有名な人でした。😅 この本を読んだら、ここで取り上げられていた山形県最上地域の城(特に志茂の手館)に行ってみたくなりました。😀2023/04/22