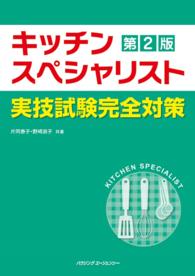内容説明
南北朝~室町期にかけて、関東を統轄した鎌倉府とは何だったのか。勢力範囲拡大の様相、鎌倉公方の幕府政治への対応と両者の対立、関東管領の動向などを描き出し、権力闘争の舞台、鎌倉府から室町期東国の実態に迫る。
目次
1 鎌倉府の展開(南関東の支配;北関東の制圧;奥羽への進出)
2 室町幕府と鎌倉府(幕政の展開と応永の乱;満兼期の鎌倉府と奥羽)
3 室町期東国社会のネットワーク(守護・国人・一揆;東国武士の信仰;東国の流通と経済)
4 合議制幕府と専制鎌倉府(合議制幕府の形成;上杉禅秀の乱;乱後の京・鎌倉)
5 鎌倉府と室町幕府の対立(足利持氏の自立;将軍義教の登場;持氏と義教;永享の乱へ;結城合戦に;嘉吉の乱と東国)
著者等紹介
小国浩寿[オグニヒロヒサ]
1962年、神奈川県に生まれる。1985年、中央大学文学部卒業。1988年、中央大学大学院博士前期課程修了。2000年、明治大学大学院博士後期課程修了。現在、都立高校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
17
248頁。鎌倉府は、たしかにその初めは、室町幕府による東国支配のための領域的出先機関として出発した。しかし、そこが武家の都であるがゆえに、安易には鎌倉を家臣に任せることができず、親族に任せ続けたことは、時間の経過に従って歪みを生み、かつ拡大していった。皮肉なことにその原点は、尊氏が、信頼する弟の直義に東国支配を任せたことであった。その後、兄尊氏と弟直義が決定的に決別することで引き起こされた。観応の擾乱は尾を引き、旧両派の確執は初期の鎌倉府体制を常に動揺させ続けることになったのである。2022/10/10
翠埜もぐら
12
観応の擾乱を経ての鎌倉府設立から永享の乱、結城合戦そして嘉吉の乱での足利義教の死までの東国史。室町幕府の出先機関として始まった鎌倉府が将軍と血が薄くなるにつれて急速に独立性を高め、あまつさえ公方による将軍職就任の強い野望まで持つのですが、これに在地の武士、下向して土着化した一族など、多様な背景をもった集団が存続と拡大のために複雑に絡み合います。享徳の乱を理解するため遡ってきたのですが、乱後の公方と上杉氏の行末も興味のあるところなので今度は流れ下っていく予定です。2021/03/09
組織液
11
南北朝の動乱をへての鎌倉府の成立から東西公方の対立、そして永享の乱での破滅という一連の東国史を概論で知ることができます。少々情報が古い点も否めませんが、一般書で持氏を再評価した画期的な書籍なので現在でもとても参考になりました。2023/11/12
bapaksejahtera
11
これ迄何冊か東国史の書籍を読んだがいずれも短い時代についての著作であった。本書は14世紀半から15世紀半。中央で言えば足利義満の死から義教の暗殺。関東では鎌倉公方基氏から持氏の敗退までを夫々対応させながら詳述する。鎌倉を含む相模と武蔵、房総三国や常陸、北関東の両毛二国。更にその背後にあってこの期のうちに鎌倉府の支配下に置かれることとなった奥羽諸国の関係が強い関係を持って動いていたことが理解できたし、黒衣の宰相満済准后他高僧の関与、軍記物の変容や般若経開板への寄進など多方面の記述が豊富で、良い読書となった。2021/08/07
読書行きの電車に乗ろう
5
鎌倉府は二代氏満からすでに幕府に対して反抗的な態度を示していた。それは自らの勢力圏の拡大を目指す上で必要となる北関東や奥州が幕府と繋がっており、また関東管領である上杉氏が幕府と鎌倉府の協調を意図していたことが背景にある。結果として二代氏満は明徳の乱に、三代満兼は応永の乱に呼応する姿勢を見せ、四代持氏は関東管領と戦った結果幕府の追討を受け滅びてしまう。氏満が挙兵の動きを見せたさいに、幕府は懐柔策として奥州を鎌倉府の管轄に入れたというのは、幕府としてもある程度鎌倉府に融和的な態度を見せていたということだろう。2018/02/11