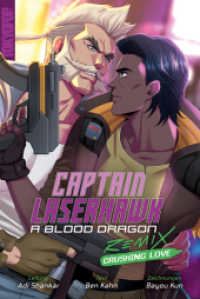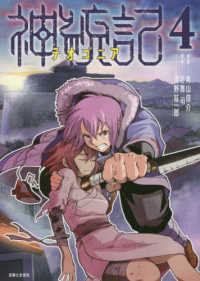内容説明
史書を読むことは歴史の楽しみを知ることである。古代から近代にいたるさまざまな歴史書二九編をとりあげ、エピソードを盛り込みながら成立事情やその性格、面白さをわかりやすく紹介。読者を史書の魅力へと誘う名著。
目次
日本書紀
続日本紀
日本後紀・続日本後紀
文徳実録・三代実録
日本紀略
古事記
風土記
古語拾遺
旧事本紀
扶桑略記〔ほか〕
著者等紹介
坂本太郎[サカモトタロウ]
1901年静岡県浜松市に生まれる。1926年東京帝国大学文学部国史学科卒業。1932年東京帝国大学大学院を満期退学。東京帝国大学教授、東京大学史料編纂所長、國學院大学教授を歴任。1982年文化勲章受章。1987年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
94
坂本先生は我々が大学受験の時は井上光貞先生と並んで日本史では有名な方でした。その先生が日本史の基本である古代から明治時代までの24の史書についてわかりやすい解説をしてくれます。日本書紀、古事記、風土記、大鏡、平家物語、太平記、日本開化小史など文学作品に近いものなどもあり参考になりました。2015/11/04
南北
36
日本の史書を「日本書紀」から明治時代の「日本開国小史」までを取り上げて論じている。同じ著者の「日本の修史と史学」と似ているが、こちらの方が内容に踏み込んでいるという印象を持った。例えば古代の地方の区画は国-郡-里となっており、「日本書紀」では「郡」だったと記されているが、「評」と書かれた木簡が発見され、かつては「評」だったというのが現在の定説であり、決着が付いたように見える。しかし著者は「日本書紀」が「評」ではなく「郡」だったと記している理由については今後探求すべきこととしていて、私も同意見だ。→2022/07/16
マウンテンゴリラ
1
私自身、一般読者として歴史に興味がある方だとは思うが、史書というものは、専門家や作家が調査,研究のために読むものという認識であった。そのため馴染みが無く、そもそも原書を読む言語的教養もない、というのが正直なところである。しかし、本書に挙げられている史書に関しては、ほぼ書名ぐらいは聞いたことがある、にもかかわらず、ほとんどその内容については知らなかった。自分の無知を棚に上げて言うのも気恥ずかしいが、これが日本の歴史教育の実態であると言えるかも知れない。本書により初めて、史書をダイナミックな読み物と、→(2)2024/03/05