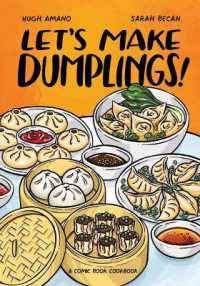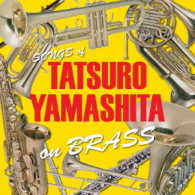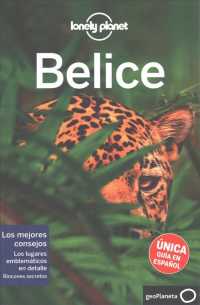出版社内容情報
★日本経済新聞 2007.12.9 に書評され大反響!(評者:安部龍太郎氏(作家))
内容説明
「天下分け目」と謳われてきた関ヶ原合戦と、徳川幕藩体制の確立のために不可避であった大坂の陣。両合戦をめぐるさまざまな定説に新たな見解を示し、豊臣・徳川が覇権をかけて繰り広げた複雑な政治ドラマの真相に迫る。
目次
天下分け目の戦 プロローグ
1 関ヶ原合戦前夜の政治情勢
2 会津征討と三成の挙兵
3 関ヶ原合戦
4 徳川幕府の成立と二重公儀体制
5 大坂の陣
幕藩体制形成における両合戦の意義 エピローグ
著者等紹介
笠谷和比古[カサヤカズヒコ]
1949年生まれる。1978年京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得。文学博士。国際日本文化研究センター研究部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かいと
24
大坂夏の陣の時の戦いで、道明寺の戦いや真田幸村(信繁)が家康の本陣に突っ込んだ戦い以外に、たくさんあったんだなぁと思いました。前田利家が死んだ後に石田三成を襲撃する計画があったことを初めて知りました。2016/07/01
孤独な読書人
15
関ケ原合戦はあくまでも豊臣政権内での争いでありその合戦に勝利したといっても徳川家康の権力掌握はあくまでも豊臣政権内でのものだった。関ケ原から大坂の陣の間の政治体制は豊臣家と徳川家による二重体制であり、それは家康個人の力量に依存する形で安定していた。 そして徳川体制を確実にするためにはこの二重体制の解消が必要であり、それは家康が生きている内果たさなければならないものだった。2018/07/15
Eiki Natori
9
来年の大河ドラマのため、だけど秀長の記述はなかったが・・・ 歴史小説などで語られているような「定説」と史実の違いを明確にしている本であり、歴史として正しい見解が書かれているので、この時代について知りたい場合は必読の本ではないだろうか。 小山の評定についての正しい見方、秀忠の到着が遅れたことは失策とはいえないこと。関ヶ原後も秀頼には一定の気を使っていたこと、逆に大仏鐘銘事件は徳川の「言いがかり」ではなかった説など、固定的な歴史観を覆す内容になっているのが興味深かった。2025/08/06
河童
4
個人的にどうも好きになれない家康。淀殿と秀頼の無念さはいかばかりか。真田や毛利の活躍むなしく秀吉方は破れ徳川方が世を制す。家康の冷静さと冷徹さが読後に残った。2018/08/17
takao
3
ふむ2025/04/03