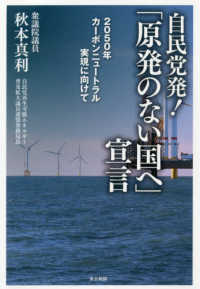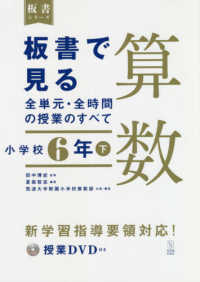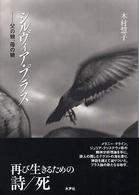内容説明
武家の棟梁をめざし、熾烈な争いを繰り広げた源氏と平氏。歴史のロマンあふれる源平合戦の全貌とその時代を描く。一ノ谷合戦「坂落とし」の真相に迫り、また戦の中の民衆の姿を描くなど、源平争乱の歴史的意味を問う。
目次
「源平の争乱」前史―保元・平治の乱
1 内乱の勃発
2 東国源氏武士団の挙兵
3 都の平氏と鎌倉の源氏
4 平氏都落ちと義仲の戦い
5 義経の戦いと平氏滅亡
6 源平争乱における戦争の実態
「源平の争乱」の歴史的意義
著者等紹介
上杉和彦[ウエスギカズヒコ]
1959年生まれる。1988年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得。明治大学文学部教授。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとまる
6
とかく義経中心に語られがちな源平の合戦を、その本質から捉え直そうとする試み。富士川の合戦の経緯に飢饉による兵糧調達の問題が論じられていないことと、倶利伽羅峠の合戦が砺波山の合戦となっているのが気になった。著者もあとがきで述べているが、義経神話を払拭するために総じて義経へのあたりが厳しい。2023/06/27
河童
6
源頼朝が鎌倉幕府を築く前、北海道を除く日本全域を巻き込んだともとれる源平の争乱です。なによりも頼朝の策士ぶりが際立つように私には感じられた。戦争の日本史シリーズ6冊目。幾多の殺し合いが歴史に刻まれていると思うと不謹慎な言い方になってしまいますが、このシリーズとても面白い。へたな小説などよりずっと。次は「蒙古襲来」です。2018/03/06
印度 洋一郎
2
この本の記述の範囲は、前史としての保元の乱から、頼朝が義経探索のために諸国に守護地頭職をおいた文治元年(1185)まで。とかく頼朝と平氏の動向ばかりが強調される通史に対し、義仲、甲斐源氏、都の寺院勢力の動向や四国、鎮西(九州)の戦局まで網羅しているので、正に日本史上初の全面的内戦の様相がわかりやすい。一次資料に当たることによって、吾妻鏡や平家物語が偏った史観によって書かれたものであることもわかる。義経伝説に対してアカデミックな立場から容赦無いツッコミをしているのもとても面白いが、賛否が分かれそう。2011/01/29
ひろただでござる
1
単なる軍記物語からの引用解説ではなく、源氏と平氏という武士集団の政権を掌握する戦いが日本と日本人に与えた(であろう)影響の大きさと深さに気づかせてくれた。この本の主旨から外れるかもやけど「朝敵」となって滅んだ平氏を当然だと蔑むことなくその運命を「あはれ」と捉える気持ちが「平家物語」を永らえさせてると思う。余分やけど「壇ノ浦の合戦」では鶴田錦史の琵琶が頭の中で響き、カール・セーガンの「人為選択」が浮かんだ。2022/04/21
ゆの字
1
九州や四国の平家家人の動きが詳しく記されていたのがよかった。範頼を評価して、義経を過剰に持ちあげないところもよし。合戦図もわかりやすくて、理解しやすかった。2021/04/07
-

- 和書
- プラグマティック化学