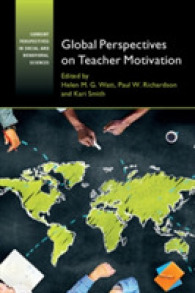内容説明
江戸時代に生きた数多い農民たち。その日々の暮らしや村の環境はどのようなものだったか。近世史の泰斗が蘊蓄を傾け、分かり易く農民と農村の実態を解き明かす。半世紀を超えて読み継がれた不巧の名著、完整な新版で甦る。
目次
1 序論
2 租税制度
3 行政制度
4 農民の統制
5 農村の伝統と住民
6 農家の生活とその変化
著者等紹介
児玉幸多[コダマコウタ]
1909年長野県に生まれる。1932年東京帝国大学文学部国史学科卒業。第七高等学校造士館教授、学習院大学長、東京都江戸東京博物館長などを経て、学習院大学名誉教授、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
t
3
部分的に読んだ。百姓の生活は牛馬のごとく、役人は横暴を極めていたという悲惨な百姓像が書いてある。巻末の解説によると、現代では百姓の豊かさを強調する風潮だが、規則に縛られていた事実を忘れてはならないとある。2010/11/03
wuhujiang
2
租税制度などの行政制度から村の制度、農民の日常生活から年中行事まで、まさに農民生活史というタイトルにふさわしいほんであろう。たいへん厳しい農民の暮らしが描かれている。あとがきにもある通り、「"おもったより"自由で明るい農村」論は近年多いように思える。前述のような本の著者は本書にある「重税に村内の階級/相互監視で自由のない厳しい農村」を前提に記述しているはずであるし、我々読者も「厳しい農村」を前提に「明るい農村」論を読まなくてはならないと感想を抱いた。2021/05/01
カムラ
1
当時の物品や習慣の名称といった専門用語が分からないから難しく感じたけど、分からないなりにも江戸時代の農民の暮らしが頭の中で風景として浮かんできて理解は進んだ実感がある。「江戸時代の人はなんやかんやで余裕もあり自由な部分があったよ」という話に持っていく本を複数読んでいたので「こんなに悲惨で苦しい絶望的な環境だったのかな?」と疑問に思ったけど、解説の「近年は農民の自由度の高さを強調されがちだが、本書で紹介される法令に見るように厳しい統制の中に置かれていたことを忘れてはならない」という指摘でなるほどと思った。2024/08/17
-

- 電子書籍
- Sea you! ~凍結スキルで最強の…