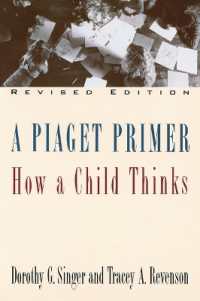出版社内容情報
江戸時代、多くの参宮客で賑わった伊勢。神宮領ではケガレを避け、清浄さが求められたが、その実態はいかなるものだったのか。ケガレを避ける方策、神主の人事と勤務実態、街道沿いでの商売、恋物語と女性たちの人生…。厳粛性の裏に世俗性・卑俗性を持ち合わせた参宮文化と、伊勢に生きた人びとを活写。伊勢参りの舞台の、個性豊かな社会を描く。
内容説明
多くの参宮客で賑わう伊勢。神聖たる地の実態はいかなるものだったのか。ケガレを避ける方策、神主の勤務実態、街道での商売、女性たちの人生…。参宮文化に潜む卑俗さと人びとの営みを通して描く、個性豊かな社会。
目次
伊勢の実像に迫る視角―プロローグ
参宮客と「ケガレ」の回避(参宮客を迎える芸能民;被差別民の参宮;仏教と参宮)
神宮領の「清浄さ」のしくみ(「死穢」の判定;「なかったこと」にされる死―速懸;動物のケガレの除去―犬狩)
御師の実態と参宮文化(御師と伊勢神宮;伊勢での案内と接待;不埒な参宮客と神主;神主の人事制度;神主の勤務実態と外部評価)
参宮街道沿いの人びと(御師と上方旅籠屋の客引き;街道の諸稼ぎ;参宮街道恋物語;愛と憎しみの人間模様)
伊勢が迎えた近代(「異国」の接近とケガレ意識;異国認識の諸相と維新期の転換)
伊勢の近代化の光と影―エピローグ
著者等紹介
塚本明[ツカモトアキラ]
1960年、愛知県に生まれる。現在、三重大学人文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
20
お伊勢さんに参った人々ではなく、彼らを受け入れる側の地域社会や神職にスポットを当てる。「御師」と「講」が紡いだ参詣ネットワーク。遊女たちの世界。参拝路の治安状況。とりわけ、穢れをどう扱ったのか?という神道の聖地ならではの問題に着目したのがユニーク。死穢を避けんがため、墓に着くまでは死んでいないことにする(着いたら即死→速攻で埋葬!)独自の葬法「速懸」など、奇想天外な穢れ対策がいくつも出てくる。2025/04/07
アメヲトコ
12
2024年4月刊。近世有数の聖地として多くの参宮客を集めた伊勢神宮。神宮は清浄というイメージを守るためにはケガレを避けねばならないものの、それを厳密に守ると都市が機能せず、ひいては参宮客への迷惑になってしまう。そうした理念と現実の間で伊勢神宮側がどのように折り合いをつけてきたのか。白黒はっきりさせる世界とは異なる、いい加減なようでいて絶妙な柔軟さが面白いです。前著『近世伊勢神宮領の触穢観念と被差別民』とも合わせて読みたい一冊です。2024/05/30
tokumei17794691
3
・江戸時代の旅の本は何冊か読んだ。ほぼ「旅人視点」だった。本書は、「観光地(伊勢)視点」なのが新鮮だった。住人自治組織やその上の山田奉行所の統治について、細々と書いてある。神宮が、現実といかに「ケガレ」の折り合いを付けるかの、知恵や苦悩が分かる。・被差別民との同火への対応、神仏分離が、神宮主体でなく、山田奉行所(幕府)主体であったことに驚いた。神宮はこれらに対し寛容なのにもかかわらず、奉行所がなぜ被差別民との同火、神仏習合を問題視したのかについては、ほとんど書かれていなかったのは残念。2024/04/29
柘植 公人
1
p482025/05/22
-

- 電子書籍
- 伯爵令嬢は引きこもりたいです!【タテヨ…
-

- 電子書籍
- アトム ザ・ビギニング(6) ヒーロー…