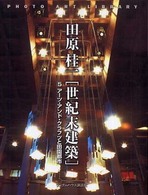出版社内容情報
温泉旅行は、どのように今日のような身近なレジャーとして定着してきたのか。観光遊興と湯治療養の両面をふまえ、その歴史を辿る。旅行形態や費用感、交通・情報インフラなど、旅行をめぐる社会環境が変遷するなかでの温泉地側の対応にも言及。日本人の温泉愛とそれを支えた屋台骨に着目し、江戸から現代へ至るまでの温泉旅行の通史を描き出す。
内容説明
温泉旅行は、どのように今日のような身近なレジャーとして定着してきたか。旅行形態や費用感、交通・情報インフラなどの変遷を追い、そのなかでの温泉地の対応にも言及。江戸から現代までの温泉旅行を通史的に描く。
目次
温泉旅行という文化―プロローグ
温泉旅行の黎明―江戸・明治期
大衆化する温泉旅行―大正・昭和戦前戦時期
再興してゆく温泉旅行―昭和戦後期
多様化する温泉旅行―一九七〇年代以降
コロナ禍、そしてこれから―エピローグ
著者等紹介
高柳友彦[タカヤナギトモヒコ]
1980年、東京都に生まれる。2009年、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、一橋大学大学院経済学研究科講師、博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おせきはん
20
江戸時代から現代までの日本人の温泉旅行の歴史がまとめられています。第二次世界大戦後のヘルスセンターブームについては初めて知りました。東京から熱海への1泊旅行にかかる費用の推移を通じて、旅行が一般的になってきた様子を具体的に捉えることができました。2023/12/05
ろべると
11
近世から戦前、戦後を経てコロナ禍に至る日本の温泉旅行の変遷をまとめている。かつては湯治が目的だったが、レジャーとしての旅行が、富裕層から徐々に広がり、団体旅行が温泉地を活気づける。各地にできたヘルスセンターも温泉の大衆化を後押しする。やがてそれらも下火になり、今はインバウンドを当てにする時代に。栄枯盛衰。著者は温泉地の資源管理を研究しているそうだが、こうした学者の書いた本は往々にして調査結果の羅列にとどまり、独自の視点による新鮮な考察などがないのが物足りない。歴史的な資料としては有用になるとは思うけど。2024/05/15
ピオリーヌ
11
著者の専門分野は温泉地の資源管理であり、主に温泉地側の視点で研究を続けてきたという。通史的に日本人の温泉旅行の歴史が辿れる。「療養」の目的が中心であった温泉旅行は、近代以降、余暇活動の一つとして観光・レジャーでの利用へと拡大した。2024/02/08
takao
4
ふむ2024/04/01
にゃあ
2
江戸・明治の温泉旅行から時代の流れと温泉旅行の実情を時系列で述べた本。療養泉として活用される背景に戦争の負傷兵を受け入れていたのは知らなかった。プレート沈み込み帯に位置することで多様な泉質に恵まれているのはありがたいことだけど、衛生面含めた維持管理にかかるコストの上昇は避けられず、余暇の過ごし方など多様化してしまった現在において、持続可能な状態な温泉って難しそうだなぁと、週末日帰りレジャーのひとコマで温泉を利用する者の1人として感じた。(本当にただの感想)2024/07/21
-
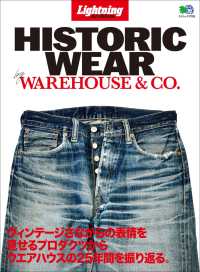
- 電子書籍
- Lightning Archives …
-

- DVD
- 縄師