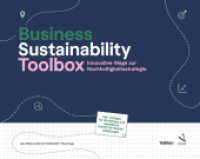出版社内容情報
仁藤 敦史[ニトウ アツシ]
著・文・その他
内容説明
「大化改新」は東アジア世界のなかでどのように位置づけられるのか。膨張する隋唐帝国への対応を迫られる高句麗・百済・新羅。三国の動向と外交政策の対立をもとに、古代日本の一大画期を新たな視点から再検討する。
目次
隋唐帝国の成立と東アジア諸国―プロローグ
唐帝国の成立と周辺諸国の対応
唐の高句麗征討と六四二年の対応
東アジア情勢と倭国の外交方針
孝徳期の外交基調と「任那の調」
孝徳政権の外交的対立
難波遷都と外交
「大化改新」論―エピローグ
著者等紹介
仁藤敦史[ニトウアツシ]
1960年、静岡県に生まれる。1989年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程史学(日本史)専攻満期退学。現在、国立歴史民俗博物館研究部教授・総合研究大学院大学文化科学研究科教授(併任)、博士(文学、早稲田大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
116
大化改新は反蘇我氏勢力による国内事情だけで起こったとされてきたが、実際は当時の外交情勢が深く関わっていた。超大国の政治圧力を受けた近隣諸国は反対派粛清による権力集中で対抗しようとするが、7世紀東アジアでも強大な隋唐と陸続きの高句麗、百済、新羅は直ちに国力強化へ動き、日本も律令制による集権国家をめざした。しかし親新羅外交に傾斜する孝徳天皇と親百済の皇極上皇の対立で政権は分裂し、孝徳帝は政争に敗れ白村江への道が開かれたと見る。日本の政治が「韓政の対立」で左右された、戦力的立場で歴史を見る重要性を教えてくれる。2022/12/03
キムチ
54
かつて学校で学んだ大化の改新が全方位的視点で眺める事に繋がった(大袈裟)筆者の文のとおり露のウクライナ侵攻は国境接する国同士の緊迫がそうでない立場の国と大きく異なることを述べる。大化の改新前夜 乙巳の変から連なる時局の変遷 孝徳期~皇極期 消失した藤原京~難波京の立ち位置(饗応の役目を担っていた筑紫の存在も併せ)が語られる。同様内容を表現を変えくど過ぎる繰り返しが目立つ。あとがきはエッセンスの様相で、これが全てと言えなくもないが。7C 唐は西方の吐蕃、東方の高句麗・百済・新羅への力関係を変容させていく。2022/12/12
MUNEKAZ
13
乙巳の変とそれに続く大化改新を、唐帝国の成立とその覇権という7世紀の東アジアの国際情勢の中に位置づけた一冊。唐の脅威をダイレクトに感じた朝鮮半島の三国、とりわけ新羅と日本の対応を比べてみると、日本側の腰の据わらなさや改革の不徹底ぶりが際立つのが面白い。朝鮮に対する抜きがたい大国意識や親百済か親新羅で定まらない外交路線など、まだまだ対岸の火事として受け止めていただけもしれないと邪推してしまう。結局、白村江での大敗という手痛い教訓を受けて、日本側も新しいステージに突入していくのである。2023/03/12
アマノサカホコ
10
大阪府図書館。なぜ乙巳の変という政変が起こり天皇に富と権力を集める大化の改新(政治改革を指す)が必要だったのか。一般的には、蘇我氏本家筋が天皇を凌ぐ権力を握っていて不満を抱き政変が起こったとされるが、それだけではなく唐がいつ攻めてくるかわからない緊迫した状況下で即断即決の権力集中が必要だとわかる。内容は濃くて640年代は百済、高句麗、新羅でも相次いで政変が起こり当時の倭国の外交交渉が理解できるようになる。大化の改新の象徴ともいえる孝徳朝の難波宮にも関連するので面白かった。激動の時代に建設された宮殿である2025/05/24
アメヲトコ
10
2022年9月刊。大火改新の意義を東アジアの国際情勢から再考した一冊です。子供の頃読んだ日本の歴史では、中大兄と鎌足が決起して横暴な蘇我氏を滅ぼし、孝徳天皇を傀儡として改革を行ったという筋書きでしたが、実際は改新の主導者は親唐・新羅路線の孝徳で、中大兄は蘇我氏以来の親百済路線の抵抗勢力だったとのこと。全然違うのね。一方で同じように政変で集権化を急速に達成した新羅に対し、日本での改新が不徹底に終わったのは、国家存亡への危機意識の差異によるものとする著者の見立てには納得です。2023/03/06
-

- 電子書籍
- さよなら、英雄になった旦那様 ~ただ祈…
-
![[図解]大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0684344.jpg)
- 電子書籍
- [図解]大学4年間の統計学が10時間で…