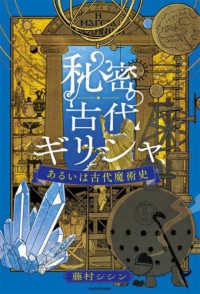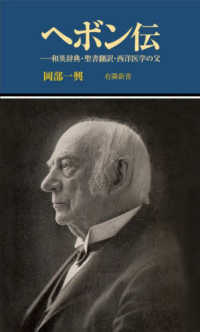出版社内容情報
様々な矛盾で幕府政権がゆらぐなか、後醍醐天皇による討幕運動が起きた。鎌倉末期十年の政治と合戦を詳述し、幕府滅亡の理由を問う。
内容説明
窮乏する御家人、旧式化した騎馬武者の合戦、悪党の活動、分裂した王家…。さまざまな矛盾によって幕府政権がゆらぐなか、後醍醐天皇による討幕運動が起きた。鎌倉末期十年の政治と合戦を詳述し、幕府滅亡の理由を問う。
目次
鎌倉幕府の何が問題だったのか―プロローグ
静かなる鎌倉の政治(北条高時政権の成立;北条高時政権の抱えた問題)
京都の状勢(延慶の山門嗷訴;後醍醐天皇がもたらした両統送立の混乱;鎌倉幕府を弱体化させら悪党追補)
動乱の時代の幕開け(正中の変;それぞれの後継者問題)
後醍醐天皇の討幕運動(元弘合戦勃発;楠合戦;六波羅探題の判断ミス;六波羅探題滅亡)
鎌倉合戦(坂東武者と坂東武者の激突;鎌倉における決戦)
鎌倉幕府滅亡後のものがたり―エピローグ
著者等紹介
永井晋[ナガイススム]
1959年、群馬県に生まれる。1986年、國學院大学大学院博士課程後期中退。2008年、國學院大学博士(歴史学)。神奈川県立金沢文庫主任学芸員、神奈川県立歴史博物館企画普及課長を経て、関東学院大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
112
室町や江戸に比べ鎌倉幕府が急速に崩壊したのは、後醍醐帝や足利尊氏の活躍のためとする説明が大部分だった。それもあるが、武家政権たる幕府が武士から見離される事態も進行していた。北条執権家は宮廷と化して権力争いに明け暮れ、元寇や悪党追捕の負担に苦しむ御家人に目を向けなかった。騎馬武者同士の合戦に固執する坂東武者はゲリラ戦を展開する楠正成ら西国の悪党に翻弄され、幕府は軍事的にも信頼を失った。そこに討幕の旗を掲げた後醍醐が受け皿となって、幕府に不満を抱く武士を団結させたのだ。権力滅亡には明確な前段階が必ず存在する。2022/06/18
ようはん
27
一昔前の日本史の本だと鎌倉幕府滅亡の始まりは元寇で御家人に恩賞がまともに与えられずに御家人の不満が高まり…みたいな記述というイメージだった。それを細かくいえば元との和平に失敗した事により臨戦態勢が続き西国警護の負担が増加、悪党の台頭に対しその鎮圧には恩賞が出ず逆に御家人の負担が増大していたという背景があった。後は小氷河期突入による東北地方の荒廃、東国の騎馬武者に対する楠木・赤松ら悪党のゲリラ戦術の優位性も印象に残る。2022/08/31
coolflat
19
227頁。鎌倉幕府滅亡の理由。今ひとつの問題が騎馬武者である。軍事担当権門である鎌倉幕府の主力部隊であるが、朝廷は鎌倉幕府の武力を無償で使う論理を創り出し、畿内の治安維持活動に六波羅探題・守護・地頭を使役した。その結果、畿内の御家人は鎌倉幕府から命令が届いても形式的に実施するだけになり、元弘の変では六波羅探題が出動を命じた軍勢が出てくるが本気で戦わない最悪の結果を招いた。朝廷から頼まれて悪党追捕の軍勢をたびたび出した六波羅探題は、赤松氏が本気で六波羅探題に向かって攻めてきたので御家人に出動を命じた。2024/10/04
MUNEKAZ
18
タイトル通りの一冊。後醍醐天皇の蜂起につながる鎌倉時代末期の政治状況に対するマクロな分析と、実際の戦闘で幕府軍が敗れたミクロな要因を論じている。朝廷内での皇統巡る対立と、それを裁き切るだけのリーダーシップを発揮できない北条高時政権の構図。とくに持明院統、大覚寺統、後醍醐天皇の3派に別れた際、後醍醐を支援する勢力が幕府におらず、蜂起に至らせたというのは納得。また悪党VS幕府軍という非対称戦のような形相を見せる畿内の攻防戦に対し、坂東武者・騎馬武者同士の正面対決となった鎌倉攻防戦という違いも印象的である。2022/04/20
フランソワーズ
15
望まない”全国支配”を課せられたゆえの、幕府の責務拡大。それが御家人に負担増となってのしかかり、疲弊させた。中でも悪党の跳梁は何の得分の得られないために徹底されず、世情の悪化を招いた。さらに自浄作用が働かなくなった天皇家の内紛にも対応しなければならないことによって、後醍醐のような異分子が生まれ、世は倒幕に傾いていった。→2022/11/09
-
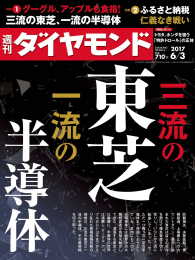
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 17年6月3日号 週…