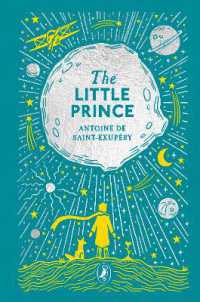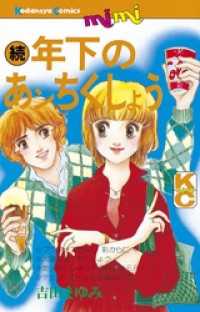出版社内容情報
「刀」は誰が差すものか? 武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿を追い、「帯刀」の本当の意味に迫る。明治維新は「武士」から刀を奪った―。刀を腰に差す「帯刀」=武士の特権という今日の?常識?は、はたして正しいのか。江戸?明治初年まで、誰が、何のために帯刀し、人々のまなざしはいかに変わっていったのか。虚栄と欲望がからみ合い、武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿を追い、「帯刀」の本当の意味に迫る。
帯刀とはなにか―プロローグ/帯刀の誕生と変質―武器・ファッション・身分標識(刀・脇差を帯びること/帯刀規制のはじまり/百姓・町人の脇差)/身分標識としての帯刀―「帯刀人」の登場(非常帯刀の登場―京都の帯刀改/天和三年令の弛緩/帯刀の特権化と整備/帯刀へのまなざし)/虚栄と由緒と混乱と―ひろがる「帯刀」のゆくえ(帯刀に魅せられて/「士」に紛れゆく者たち/帯刀と身分秩序/白刃に血が滴るとき―終わりの序曲)/明治初年の帯刀再編―消えゆく身分標識(平民帯刀の整理/三治一致と藩の帯刀許可/暮往く帯刀人の時代)/身分標識から旧弊・凶器へ―貶められた最期(脱刀がもたらしたもの/帯刀意義の変質/廃刀の時代/変わる常識、消えゆく習慣)/刀を差せない日―エピローグ
尾脇 秀和[オワキ ヒデカズ]
著・文・その他
内容説明
「帯刀」=武士の特権という今日の“常識”は、はたして正しいのか。江戸~明治初年まで、武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿と維新で消えゆくまでを追い、「帯刀」の本当の意味に迫る。
目次
帯刀とはなにか―プロローグ
帯刀の誕生と変質―武器・ファッション・身分標識
身分標識としての帯刀―「帯刀人」の登場
虚栄と由緒と混乱と―ひろがる「帯刀」のゆくえ
明治初年の帯刀再編―消えゆく身分標識
身分標識から旧弊・凶器へ―貶められた最期
刀を差せない日―エピローグ
著者等紹介
尾脇秀和[オワキヒデカズ]
1983年、京都府に生まれる。2013年、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。現在、神戸大学経済経営研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
akiakki
bapaksejahtera
in medio tutissimus ibis.
テキィ
hiro6636