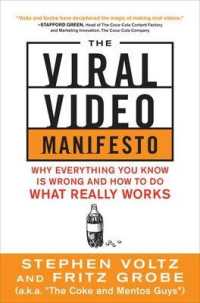出版社内容情報
桓武平氏とされ、相模国随一の大豪族と呼ばれた三浦氏。今、その実像が見直され始めている。武家政権の成立を支えた義明・義澄、朝廷に対する顔役の義村ら代々幕府の重鎮を輩出しながらも、宝治合戦でいったんは滅ぶ。しかし、佐原系三浦氏や三浦和田氏らは中世末まで存続し、その足跡は全国に及ぶ。三浦一族の興亡から日本中世史を見つめ直す。
内容説明
近代、科学の進歩や機械化により「腐敗」の問題を断ち切った日本の酒づくり。全国の老舗酒造家たちは、酒税の改変や災害、不況、戦争など、激動の時代をいかに乗り越えてきたのか。酒造五〇〇年の歴史を鮮やかに描く。
目次
いつから“日本酒”というようになったのか?―プロローグ
日本酒造地の誕生
近代の日本酒造地
酒税と科学的な日本酒づくり
戦時下の日本酒造業
現代の日本酒事情―酒造地の変動
“日本酒で乾杯”―エピローグ
著者等紹介
鈴木芳行[スズキヨシユキ]
1947年、新潟県に生まれる。1974年、中央大学文学部史学科国史学科卒業。1978年、中央大学大学院修士課程文学研究科国史学専攻修了。現在、中央大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件