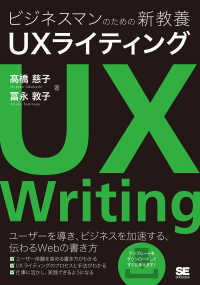内容説明
古代国家の繁栄を支えたのは、戸籍を作成し租税を徴収した郡司や国司ら地方官人だった。村の生活を指示した木簡や、墾田開発・庄園経営などを伝える古文書から、古代の“お役人”の仕事を紹介し、その活躍を描き出す。
目次
平城京の繁栄を支えたもの―プロローグ
国・郡の支配者たち
郡司とその周辺
評から郡へ―郡司制の成立
国司と結びつく人々―郡司の変質
村のなかの律令制―エピローグ
著者等紹介
中村順昭[ナカムラヨリアキ]
1953年、神奈川県に生れる。1982年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。文化庁文化財保護部美術工芸課文部技官、文化財調査官などを経て、日本大学文理学部教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金監禾重
7
雲の上の中央貴族ばかりでなく、身近な郡司層のことを知ることができて嬉しい(とはいえ私的に用水路建設などができる在地権力者だが)。国司が律令制の整備とともに新設された職であるのに対し、郡司は旧来の在地勢力を取り込んだもので、官位相当がないなど制度上の違いが多い。また時間経過とともに在地官人は中央や国司と比べ出世が難しくなり、中央支配の強化を物語っている。「郡(評)」は2つの豪族の支配地を融合させて設定され、それぞれ大領と少領を世襲した。勢力均衡や多面的な民衆支配が想定されるという。2022/11/08
check2012
3
長年の疑問が、少し氷解した〜。良かった。2015/01/06
たま
2
地方の下級官人ともなると上から虐げられてるのかな〜とか思うけど多分想像してるよりだいぶ強かだし面の皮が厚い2020/06/11
wang
2
奈良時代地方の中間管理職である郡司を中心とした人々のこと。国司は律令体制で導入され中央貴族が派遣されて来た。中国と違い郡司は地方の豪族がそのまま朝廷の支配体制に組み込まれた。大領・小領・主政・主帳がいたが、彼らが抽象豪族や有力農民で互いに牽制し合いながら地方経営に当たったことなどがわかる。他にも律令に出てこない雑人・雑掌・散人などと呼ばれる職員が登場。古代の国造・伴造・稲置や五十戸長などがそれぞれ律令体制に組み込まれていく様子。不正や利益の少ない職のため8・9世紀に体制が乱れていく歴史など。2019/10/28
はちめ
2
興味深いことが書いてありそうなんだけど全く頭に残らなかった。読解力の問題かな?2014/11/09