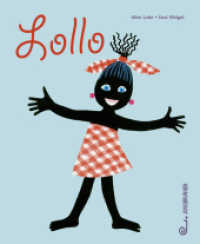内容説明
明治二年に誕生した華族の中でも、天皇に近い存在だった「公家華族」。その多くは天皇とともに東京へ移ったが、京都に残った公家たちもいた。困窮しつつも公家文化の伝統を残そうと奔走した姿を描き、華族の役割を考える。
目次
京都公家華族とはなにか―プロローグ
京都に残る公家華族
四民の上に立つ道程
困窮する公家華族
東西両京を往復する公家華族
社会を騒がす公家華族
大正・昭和の京都公家華族―エピローグ
著者等紹介
刑部芳則[オサカベヨシノリ]
1977年、東京に生まれる。2010年、中央大学大学院文学研究科博士課程修了学位取得。現在、日本大学商学部准教授博士(史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん
6
以前から華族というものの具体像に興味があったのですが、偶然図書館で目について手に取りました。特に華族の情けない部分を代表する公家系、その中でも特に残念な京都や奈良にいた華族をテーマにしているので、華族の下世話な問題が特に抉り出され、おもしろい本でした。どうやら中流以下の生活を家族だけで送るなら働かなくてもやっていけるだけの収入があったようですが、底辺華族には貴族としてふるまうのは無理があったようです。あくせくせずに、働くことは卑しいことという古き良き倫理に殉じておればよかったのにと、個人的には思います。2019/07/27
Saint Gabriel
5
お公家様ヘタレ物語を読んでいる様で別の意味で楽しく読ませてもらった。やはりお公家様は何時の時代も根性がない。弱い。2016/07/17
あられ
4
新聞の書評で見かけて、図書館で借りた本です。一言で「華族」といっても、公、侯、伯、子、男があり、新しいのも、古くからもあり、貧富の差もあり。ひとは貧すれば鈍す、不祥事もおこす、犯罪沙汰にもなり、とほほな例もあり。はたからみれば、優雅に見えても、内情は?、なのだった。2014/11/11
紫
3
明治維新の後、京都から東京へ遷都してからも京都に残った公家華族の検証本。ホントにがっつり、京都華族や奈良華族の動向や待遇について縷々とした説明が続きますので、ごめんなさい、難しくてついていけず、読み終わるまで一ヶ月半かかりました。(勤め先の空き時間でしか読んでなかったという事情もあるんですが……)スキャンダルまみれの華族の実情は目を覆うばかりですが、その手のエピソード集的な楽しさを期待して手を出すと大火傷をするのであります。星3つ。2024/10/24
コカブ
3
明治維新後に華族は東京居住とされたが、京都に残った公家華族がいた。彼らに焦点を当てた本。当初は京都の家族の力はある程度強力で、「東京遷都」ではなく「奠都」という言葉を使ったのは京都の公家に配慮したからだった。また、近衛・二条・清水谷などの名のある旧公家が東京に移ってから京都に戻っている(著者は”水が合わなかった”ためと推測する)。明治初期は輸送手段も未発達で、土葬が広まったことを考えると、東京移住=先祖と別の墓に入るという重い決断だったと著者は指摘する。その割に、東京に移住した公家が多かったのは意外だ。2018/06/18