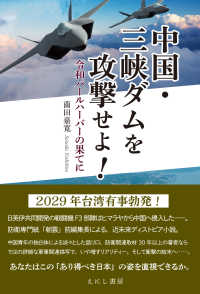内容説明
古代よりお金・鉄炮・刀剣などの「ものづくり」をしてきた日本人。和同開珎の銅含有量や偽金との関係、鉄炮や刀剣の失われた製法など、金属の成分分析から様々な史実を解明。日本の歴史を、金属という新たな視点から見直す。
目次
金属から歴史をみること―プロローグ
古代銭貨「皇朝十二銭」をさぐる(銭貨と素材;鉛同位体比による産地推定;電子線スキャニングによる成分分析;日本産原料の始まり;古和同の原料を考える)
日本刀はどのように作られるか(日本刀について;刀匠・法華家に学ぶ;鋼を作る―卸し鉄とはなにか;鋼を鍛える―折り返し鍛錬;刀に命をふきこむ―焼き入れ)
鉄炮の製法をめぐって(鉄炮について―失われた技術を探る;鉄の基本的知識;大鍛冶の復元をめざして;問題の解決)
ものづくりの復権をめざして―エピローグ
著者等紹介
齋藤努[サイトウツトム]
1961年神奈川県に生まれる。1988年東京大学大学院理学系研究科化学専門課程・博士課程修了、理学博士。現在、国立歴史民俗博物館研究部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
10
著者は、科学的調査により、日本の歴史の中での金属資料の素材、製作法、技術などを解明する研究者。文献史学では明らかにし得ない部分が科学のちからにより、分かるのが興味深い。例ヘば日本製銅銭の銅の産地推定に繫つたり、皇朝十二銭の素材比率の分析から銅不足への対応が跡づけられたりする。刀剣鍛錬技術や鉄砲の鉄生成の話はかなり専門的だが、歴史の中の技術史研究のなかでかうした裏付けが得られることは、学会が共有すべき財産なんぢやないかと思ふ。2022/07/16
Ami
3
古代の貨幣の鉛同位体から産地を推定し、刀匠に学んで古の小鍛冶・大鍛冶の技を再現する。具体的な工程が載っている本を読んだのは初めてで面白い。刀剣女子ならきっともっと興味を引かれることでしょう!古代から日本人は金属器を作り出してきた。日本人の高い技術力に改めて感動。2019/02/18
yraurb
3
日本で鍛えられた鉄である貨幣、刀、鉄炮について、含有される重金属の分布や和鉄の製鉄方法の変遷について解説した本。鉛の含有量変化についてとか、刀用に鍛えられた鉄がいかに特異な存在なのかとか、そういう面白い話がたくさん詰め込まれていた。中でも一番面白かったのは「大鍛冶」の復元研究。本では中途までの復元だったのでその後をぜひ知りたい。2017/02/07
転天堂
2
皇朝十二銭、日本刀、火縄銃という日本史上の金属加工について、文化財科学(自然科学)の視点から取り組んだ研究成果をやさしく解説している。日本刀、火縄銃の鉄加工について、どのような形で技術を確立していったのか、謎は尽きない。2021/11/15
三条院アルパカ
2
知られざる鉄の科学を読んだのでふと思い出して再読してみたところ、初読時になんとなく読み落としていた部分がいくつかあったことに気が付いた。浸炭・脱炭の部分、大鍛冶の再現の部分も前よりよく理解できたと思う。以前この本を読んだあと、日本刀もたくさん見て回ったし、国立博物館ではたまたま皇朝十二銭の展示を見る機会にも恵まれた。というよりこの本をたまたま手にすることがなかったら博物館の皇朝十二銭に目を留めることもなかっただろう。こういう読書が開く新しい知識との縁というものは確かにあるものだとしみじみ。2017/04/20
-

- 電子書籍
- 猫なのにオオカミ一家の養子になりました…
-
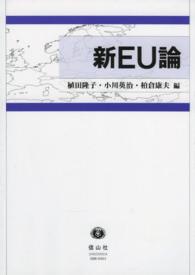
- 和書
- 新EU論