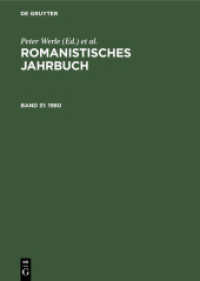内容説明
結婚・出産・死亡の記録から、個人のライフコースを明らかにする歴史人口学。宗門改帳を分析し、江戸時代の「少子化」社会や子ども手当「赤子養育仕法」を解明。現代の少子高齢化などの問題解決への手がかりを提示する。
目次
歴史人口学の半世紀―プロローグ
村の人口誌を読む
江戸農民の生と死
人口から見た東西日本
江戸の都市社会
人口増加への転換点
人口減少社会をどう生きるのか―エピローグ
著者等紹介
浜野潔[ハマノキヨシ]
1958年、東京都に生まれる。1989年、慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、関西大学経済学部教授、博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
18
江戸時代は今と比べて子供が死に易く故に平均寿命も30代後半であったが、子供の中に幼児を見れる姉がいたり祖母が同居していたりすると生存率が上がるという話等、成る程と思う内容は多かった。現代と同じく少子化が生じていた二本松藩のある農村のケースでは初婚年齢は早いが妻が奉公に行く傾向により夫婦がいる時間がない、産む子供の性別バランス(最初に女子、次に男2人)を整える中での間引きが行われていた話も興味深い。2024/12/07
Haruka Fukuhara
12
歴史人口学って何というか、あまり夢がないというか面白くないというか、データから人口を推論する発想を最初に思いついた人はすごいと思うけど、それだけっていう感もありますね。フランスで戦後に誕生したとのことで、元々は教会の資料とかから当時の人口を推測するという手法は画期的だった様子。それを日本の江戸に当てはめて(よく読まなかったけど、寺社関係の資料とかから?)わかったことが色々と載っていました。2017/05/31
ともたか
10
歴史は事実で推し量るのが正しく歴史を知ることに通ずる。 その一つの指標が人口学であるようだ。磯田さんのように古文書で 歴史を読み解く学者もいる。ただその古文書は市井の普通の人が 書いたものでなければ意味がなくなる。ここが注意点である。2015/12/21
犬養三千代
6
名もない江戸時代の庶民のライフコースを人口分析で読み解いた本。 最後まで読んだが、やはりエマニエル·ドットのほうがおしろいと思った。2018/05/04
maqiso
3
年ごとの個人の住所や年齢の記録から地域の経済や文化を推し量れるのが面白い。各村の年次変化のような細かい情報が、東西での家族の形態の違いや都市の行き詰まりと農村の発展など全国的な傾向を説明していって楽しい。2019/02/18
-
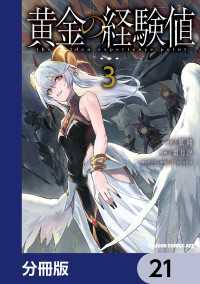
- 電子書籍
- 黄金の経験値【分冊版】 21 ドラゴン…