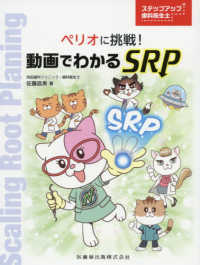内容説明
日本の農耕文化はどのように始まったのか。一万年前頃中国大陸に誕生した農耕は、気候の変動を契機に技術と人の移動を伴いながら、朝鮮半島を経て日本に到達する。最新の考古学が初めて明らかにするイネの来た道。
目次
農耕とは何か―プロローグ
縄文から弥生が意味するもの
環境の変動と農耕の広がり―第一段階
イネ栽培の始まり―第二段階
農耕社会の誕生―第三段階
縄文から弥生へ―第四段階
日本農耕文化の起源―エピローグ
著者等紹介
宮本一夫[ミヤモトカズオ]
1958年、島根県松江市に生まれる。1984年、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。京都大学文学部助手、愛媛大学法文学部助教授をへて、現在、九州大学大学院人文科学研究院教授(考古学専攻)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nori
7
Despite 縄文時代 is interesting, give up to read as archaeological approach is too difficult for me, although I know there is no other way to study this theme. In this sense history is easier study than such physical research.2021/08/03
ほっちょる
4
日本列島への農耕の伝播について、そのルートや渡来人の形質等の問題はこれまでにも論じられてきた。しかし、東北アジア全体を見回して、考古学的な根拠から、そのプロセスを論じた試みは、ほとんどないのではなかろうか。とりわけ、筆者が中国で実施した学際的な発掘調査とその成果による裏付けを通して、気候変動が栽培穀物や人の移動、文化の伝播をもたらしたことを、段階的に論じた点は興味深かった。2018/05/19
ナオ
3
AMSと較正年代、ボーリング調査、シリコンと顕微鏡で、農耕の開始は燕に押された朝鮮難民ではなく、自然環境変化による農耕民の移動と判明した。というところか。 2011/10/18
Junko Yamamoto
2
詳しく知りたい点が多々あった。玉、菅玉は日本になかったこと。縄文時代は双系社会であった、あったなど。2020/02/07
kaigarayama
2
イネそのものだけではなく、土器や石器などの考古資料を含めてイネの伝播ルートを明らかにしているのが特徴。また、発掘調査によって仮説の検証を試みる「最古の水田を求めて」のくだりは研究の現場が見えておもしろい。ただ、文章が読みにくいように感じる。この点は編集側にも責任があると思う。2011/08/07