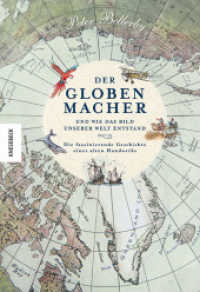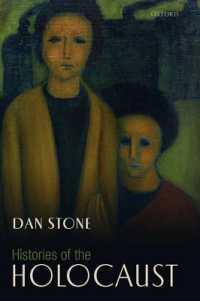内容説明
江戸時代の“捨て子”は、どこに、どのように捨てられ、拾われたのか。ともに添えられたモノや手紙に託した親の思い、捨て子を貰う人々、江戸にもあった赤ちゃんポスト構想。そこから見えてくる捨て子たちの実像を描く。
目次
捨て子へのまなざし―プロローグ
なぜ捨て子か
親の手紙
つけられた名前
捨てる女、捨てる男
捨て子から棄児へ
『誰も知らない』によせて―エピローグ
著者等紹介
沢山美果子[サワヤマミカコ]
1951年、福島県に生まれる。1979年、お茶の水女子大学大学院博士課程人間文化研究科人間発達学専攻修了博士(学術)。現在、岡山大学、ノートルダム清心女子大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
54
名も残さず、生まれた無数の「誰も知らぬ」子・・その命の連鎖に光が当てられることはない。堕胎・捨て子・間引き・・それぞれの事情を探って行くのは興味深かった。近世史上、「捨て子」から「棄児」へ展開して行く・・現代に繋がる「子供らとその背後の社会」がいか様な情景かを種々のモノから立証。江戸後期は「貧困のみならず諸々の原因」で捨てられ、傍らにはモノを添えてあった。「他人の家」で命を繋げるようにとの親の思いがあったと。そして棄児はやむを得ぬものと。親のモラルのみに問題を還元してはならぬの言葉が泣かせる2020/03/27
びっぐすとん
16
図書館本。『くそじじいとくそばばあの日本史』で引用されていたので。私が子供の頃はまだ「捨て子」という言葉を耳にすることがあった。親の死、困窮により昔から捨て子はあった。生類憐れみの令が捨て子救済を促進した反面、捨て子を増加させたとは知らなかった。衣類やお守り、初髪、臍の緒に書状を添え、養ってくれそうな屋敷の前に捨てた親心。中世よりは子供の命の価値が上がった近世。血縁より「家」の存続が第一の時代であればこそ養子への抵抗が無かったことなど、今まで悪とみていたものの意外な反面を知った。生まれてすぐ捨てられる子は2021/12/16
bapaksejahtera
9
悪法として誤解されがちの生類憐れみの令を機として養育の困難な乳児を捨て赤子と親も生き延びようとする捨て子が増加した。都市では寺院や大名屋敷、地方では富貴な農民屋敷の夫々近傍にタイミングと適地を図って遺棄される。官にあっては儒教倫理観、民にあっては地域自検断の経済的崩壊があろう。捨て子に添えられる鰹節や胞衣などの民俗的表象が時代が下るにつれて消えていく。明治に至り行政の未熟を覗う周旋業者の横行。フェミニズム視点はやむを得ないが渋沢栄一の養育院を従順な労働者の育成目的とするような記述は折角の労作を自ら貶める。2020/10/05
犬養三千代
9
江戸時代、生類憐れみの令と言えば「お犬さま」と連想するが捨てられた子供を守るシステムも生み出している。乳幼児を預かったほうに金銭がお上から支払われ、養子に出される。古文書を読み解き丹念に分析している。子のそばには手紙をそえたものもあり、「なさけなき 浮世のために 子を捨てて 我が身を立てる 親の心そ」。 2019/11/01
邑尾端子
8
中世までの日本では、育てられない子の処分といえば堕胎や間引き、つまり殺害によるものが中心だった。宣教師が「西洋のような乳児院はなく、この国の女達は不要な赤子にはすぐに石を載せて殺してしまう」と報告しているとおり。その間引き文化が棄て子文化へと移行したのは江戸の生類憐れみ令の頃からであった。また現代では捨て子というと母親が一人で捨てるイメージだが、江戸時代にはむしろ父親が家の代表として捨てるものという印象が強かったようである。面白い。2014/12/13