内容説明
古代の家族・親族関係の変化は、国家の誕生と深い関わりがあった。縄文から古墳時代まで、人骨とその墓を人類学・考古学の最新の成果から分析。現代とは異なる古代の家族や親族の実像に迫り、その歴史的意味を問う。
目次
歴史における家族・親族の意味―なぜ家族なのか(考古学における家族と親族;家族・親族の歴史的意義;日本考古学における親族論;考古学と古代史;方法の有効性と限界)
基層をなした双系社会(縄文時代の親族関係;弥生時代の親族関係;古墳時代前半期の親族関係)
父系社会の形成(「上ノ原」が解明したこと;上ノ原の集団と儀礼;後期古墳の被葬者)
家族・親族からみた古代社会(部族社会としての縄文時代;部族原理と階層構造;父系化と古墳時代社会;親族関係の変化と国家形成―エピローグ)
著者等紹介
田中良之[タナカヨシユキ]
1953年、熊本県に生まれる。九州大学大学院文学研究科博士課程中退。同大学医学部解剖学第二講座助手、文学部助教授をへて、現在、九州大学大学院比較社会文化研究院基層構造講座教授。考古学・先史人類学専攻。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
1
ふむ2023/06/22
サンチェス
0
なんとなく私たちが意識している「家父長制」とは、長男の息子が一番偉いというものだと思う。その一番偉い人が財産やらを引き継いでいくというのは時代劇でよく見ることだろうが、その仕組みはいつの時代から生まれたのだろうか。この謎を解明するために、縄文・弥生・古墳時代の墓から出土する人骨の歯冠やDNAの分析する。同じ墓に納められたのは兄弟なのか、夫婦なのか、そこに子供も混ざったりするのだろうか。教養本ではないが、仏教や神道が普及する前の日本の原風景の一端を知るにはいい本だと思う。2016/11/02
ナオ
0
なかなか九州の枠組みを出るのは難しいようだ。2012/02/06
おらひらお
0
2008年初版。タイトルからするとすこしとっつきにくい感じもありますが、文章は平易で初学者にも分かりやすいと思います。個人的には、これまでうやむやにして中途半端の理解であった、「家父長制家族」「氏族共同体」「バンド社会」「部族社会」「ムラ出自論(←これは批判するために説明)」「農業共同体」・・・といったような用語も再確認できてよかったです。2010/07/05
ハキ
0
男女一対の骨が墓から見つかると機械的に夫婦として分類したくなりそうなものだが、古い時代の墓から見つかった歯をくわしく調べるとその二人は同世代の血縁者、つまりきょうだいである可能性が高いのだという。2016/04/14
-
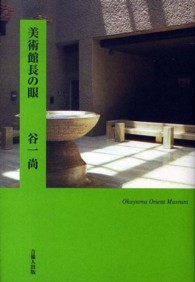
- 和書
- 美術館長の眼








