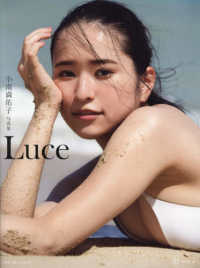出版社内容情報
☆読売新聞 2月12日(日)の読書欄にて紹介されました!
評者:苅部 直氏(東京大学助教授)
内容説明
鎖国下の江戸で、人びとはどのようにナポレオンやベトナム象などの海外情報を入手したのか。ペリーの砲艦外交やロシア軍艦の対馬占拠事件を分析。海外情報ネットワークが、ついには幕府の崩壊をもたらした姿を描く。
目次
情報の役割―プロローグ
海外情報の収集・発信の地―長崎と横浜
異国情報と江戸社会
緊迫する海外情勢と国内政治
幕末の異国船来航と情報分析
情報と幕府の崩壊―エピローグ
著者等紹介
岩下哲典[イワシタテツノリ]
1962年、長野県に生まれる。1994年、青山学院大学大学院博士後期課程単位修得満期退学。明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部教授(大学院応用言語学研究科教授兼担)、博士(歴史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
312
いわゆる鎖国下にあって、幕府が得られる海外情報は唐船からもたらされる風説書と阿蘭陀風説書、および長崎に入って来る書物等しかなかった。そうはいっても、新井白石がシドッチを尋問した時の様子(『西洋紀聞』で知ることができる)などからすれば、幕府中枢はそれ相応に世界情勢を把握してはいた模様である。本書で興味深かったのはナポレオンに関する情報である。頼山陽の『仏郎王歌』、小関三英の『ホナハルテ伝』などがあり、これらが幕末から明治維新に与えた影響は無視できないものがあるようだ。2022/10/25
kazewataru
3
形ばかりとはいえ鎖国中の江戸末期に海外情報がどのように伝達され、処理されていったのかを検証した本。主に外から入って来た情報についての内容だが、ゴロヴニン『日本幽囚記』とムールの「獄中上表」を幕府天文方がオランダ語に翻訳してヨーロッパに運び、欧州人に読んでもらおうとしていたという記述に驚き、感嘆した。結局ことはならなかったのだが、もし実現していたとしたら、日本から公式に海外に発信する情報第一号として、情報とは集めるのみならず発信しなければ意味がないという認識を、日本人が得たのかもしれない。2013/06/20
芹沢
3
主にアヘン戦争と水野忠邦・長崎奉行、ペリー来航と幕府・地方武士・庶民の情報認識の部分をゼミで読んでみた。書簡などの古文書を概観したうえで筆者の論を述べているが、結論に至るまでにもう少し具体的史料と説明が欲しいと感じた。 これを読んでみて、江戸幕府の天文方が和解御用になるまでにどんな役割を果たしていたのか興味をもった。2012/11/29
wang
2
江戸時代に情報がどのような経路・手段で伝えられたのかを知りたかったのだが、その記述はほとんどなし。存在したであろう海外情報を伝えるネットワークによってもたらされた情報に何があり、どう使われたのかが書かれている。ベトナム象が上京した時の話、ナポレオンが欧州を征服、アヘン戦争、ペリー来航の事前情報などが取り上げられ、いずれも興味深い。広南従四位白象が後の世の創作であること、黒船の凶歌や、ペリーの白旗文書なども同様に創作であることが確認できる。ロシアによる対馬占領事件などは知らなかったし面白く為になった2019/08/08
あ
0
テスト