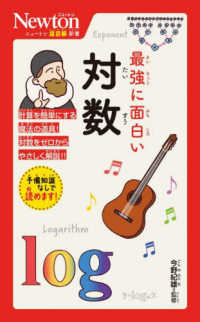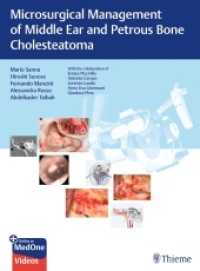内容説明
古代日本の「内」と「外」を旅した渡来人。倭国と国際社会の関係を人・モノの移動から眺めれば、「古代のわが国」というイメージとは全く別の、社会や境界が浮かび上がる。従来の「日本史」像を強く揺さぶる、東アジア交流史。
目次
渡来人と「日本」
絡み合う渡来の契機(「帰化人」と「渡来人」;王の外交と「質」 ほか)
拡散する渡来系技術・文化―五世紀の渡来人(結び付く地域・王権・渡来人;漢字文化を運ぶ人々 ほか)
渡来とネットワーク―六世紀の渡来人・渡来系氏族(錯綜するネットワーク;定着と対立 ほか)
渡来人から「帰化人」へ 七世紀の渡来人(整理される諸関係;「帰化人」へのみち)
著者等紹介
田中史生[タナカフミオ]
1967年、福岡県に生まれる。1996年、國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期修了、博士(歴史学)。関東学院大学経済学部助教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おらひらお
4
2005年初版。帰化人と渡来人の違いから、考古学の成果を交えた渡来人の位置づけの変遷までをまとめた本です。結構勉強になりました。2012/06/11
赤白黒
3
4〜7世紀にかけての倭王権と渡来人の関係について記す。文献史学が専門の著者が、文字史料と考古学の発掘成果を結合させ、当時の列島の姿を巧みに読み解いていくのが楽しい。渡来人の姿を辿れば我が国の王権伸長の過程が見えてくる。階層ごと、地域ごとに多元的であった対外関係が王権により徐々に一元化されていき、最終的には律令国家の成立に至るという。近年、世界史あるいは東アジア史の文脈から日本史を鳥瞰する試みが多くなされていると思うが、本書もその流れに属するものか。朝鮮史も併せて学べばこの辺りの事情がより深く理解できそう。2024/11/05
hyena_no_papa
2
難しい。『書紀』や百済三書が出てくると、途端に難渋する。数十年前、中公新書の上田正昭『帰化人』を読んだことがあった。内容はほとんど覚えていない。しかし、古代史の一視点として踏まえておかなければならない項目なんだろうとは思った。田中史生氏の本書は『帰化人』よりは広い視野に立って述べられているのではないかと思うが、確かなことは言えない。ただ、日本古代史は東アジア史と切っても切り離せないことだけは分かる。197頁の「ブックロード」は初めて聞く言葉だ。参考文献を読んでみたい。氏のこれからの研究にも大いに期待。2020/01/02
Junko Yamamoto
1
わかりやすい。外の異界との交流で日本の国が形作られてきたことが明瞭に理解できた。2021/01/15
遊動する旧石器人
1
「帰化人」と「渡来人」の違いがわかった。2013/08/28
-
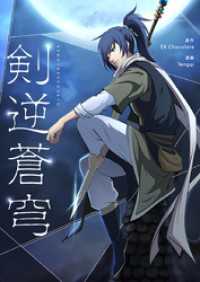
- 電子書籍
- 剣逆蒼穹【タテヨミ】第231話 pic…