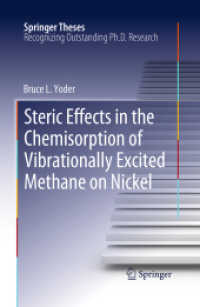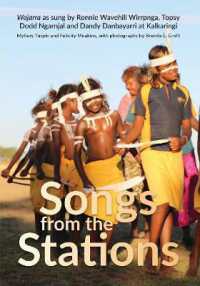内容説明
古代より人とモノが行き交う瀬戸内海。旅人としての宣教師や戦国武将たちは、そこで何を見、どんな体験をしたのか。寄港先や航路から海賊の出没スポットと遭遇時の対処法まで、知られざる中世瀬戸内海の世界を旅する。
目次
港・航路・海賊―プロローグ
厳島参詣の旅
モノ・人を運ぶ旅
キリスト教宣教師の旅
戦国武将の旅
中世の航路と港―エピローグ
著者等紹介
山内譲[ヤマウチユズル]
1948年、愛媛県に生まれる。1972年、京都大学文学部卒業。現在、愛媛県総合教育センター室長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
5
中世文書から瀬戸内海を旅した人々、交通路を維持した人々の姿を復元していた。此処に描かれた瀬戸内海のなんと歴史と文化のゆかしさよと寂れた現況から嘆じざるを得ない。鞆の価値とその衰退がなぜかということを腑に落ちさせたのは、読んでよかったという他ない。鞆が瀬戸内海の潮汐の頂点だから潮待ちの港として重要だったのね。船のサイズや航海技術の普及で中世においても湊町の興亡があったのは当たり前だが中世の長さを思い知らされた。ところで参考に上げられてる本古書価高すぎである。2018/03/09
イツシノコヲリ
2
海賊研究の第一人者が中世の瀬戸内海の航路を当時の日記などから明らかにする。三田尻(山口県防府)、牛窓、室津、塩飽など様々な港が登場する。時代が進むにつれて航海技術が発達し、航路も変化していくと分かった。また海賊は中世の瀬戸内海において大きな存在感を放っていたと実感した。個人的にはこの書籍は、榎原雅治氏の「中世の東海道をゆく」の山陽道版みたいなものだと感じた。2022/11/14