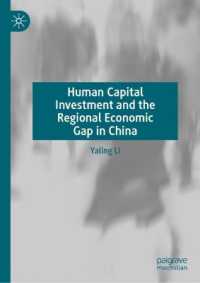内容説明
今、読経による癒しが注目されている。仏教を学ぶための読経は、日本に伝来すると祈祷や音楽・文学の中にも再構成され大きな影響を与えた。読経僧とそれを聴く人々を中心に音の世界に触れ、そのメカニズムを読み解く。
目次
読経の音
能読の誕生
読経の力
音芸と読経
読経をめぐる人々
著者等紹介
清水真澄[シミズマスミ]
1957年、静岡県静岡市に生まれる。1994年、青山学院大学院文学研究科日本文学・日本語専攻博士後期課程単位取得満期退学。現在、青山学院女子短期大学非常勤講師、聖徳大学非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
45
【阿耨多羅三藐三菩提 我が立つ杣(そま)に冥加あらせ給へ(伝教大師 最澄)】院政期から中世にかけて活躍した能読と呼ばれる読経僧と、それを聴く人々を中心に仏教の音の世界に触れ、日本人の心に響く読経のメカニズムを読み解く書。巻末に参考文献と資料。2001年刊。<仏の声は「お経」という文字に置き換えられて伝えられ、信仰によって文字から音へと再生されてきた。その音は、再生する者の精神と肉体の力によって、無限大のパワーに拡大する。/読経や念仏の数を重ねれば功徳を積むと信じて、僧も俗も読経の技量と数量を競った>と。⇒2024/07/30
なにしな
1
読経は、誰しも一度は聞いたことがあろう。仏教では僧・檀家共に、読経することそれ自体を信仰及び帰依の表れとするが、これが日本に伝来し神道と習合、和歌披講となり、神楽・催馬楽・朗詠・今様へと変化していった。インド、中国を仏教とともに経由してきた読経の技術と、これを日本人がどのように活用してきたかを眺めるのにちょうどよい。専門用語も多いので、「はじめに」「むすび」から読み始めると挫折しないかも。2018/02/06