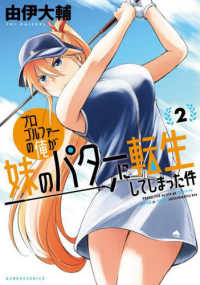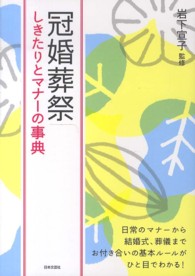出版社内容情報
698年に大祚栄が、靺鞨人と高句麗遺民を率いて高句麗の故地に建国し、926年契丹族の耶律阿保機によって滅ぼされた渤海国。いまだ謎のベールに包まれた渤海国の230年の変遷を、かつての「民族史」に捉われた、唐帝国の衛星国家や日本との友好的外交関係を中心に描くことのみに満足せず、渤海人を主人公に個性的な歴史を蘇らせた初の興亡史。,
内容説明
698年に大祚栄が、靺鞨人と高句麗遺民を率いて高句麗の故地に建国、926年契丹に滅ぼされた渤海国。謎の多い230年の変遷を「民族史」に捉われることなく、渤海人を主人公に個性的な歴史を蘇らせた初の興亡史。
目次
「武」の時代
「文」の時代
「富」の時代―海東盛国
「商」の時代
王国の解体
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
79
満洲に栄えた渤海国の通史。日本側の史料を多用している為、渤海ー日本外交史になっている面が惜しまれる。2024/06/16
ゲオルギオ・ハーン
28
7世紀末~10世紀の229年間続いた渤海国の歴史を解説した一冊。謎の国というイメージだったが、これで理解を深められた。そもそもは高句麗の亡命一族と靺鞨人による連合国のような体制をしている。強力な中央集権も軍事力もない代わりに外交関係は現実主義で唐の契丹政策に乗じることで冊封関係に入り権威を持つことに成功する。そのため、唐の滅亡とともに安定性がなくなり、単純に次の盟主として後唐を選ぶが後唐は唐のような国力がないため、先制して攻めた契丹を率いる耶律阿保機の反撃の前になんの効果もなく滅びてしまう。2022/12/13
coolflat
16
1頁。渤海国は698年に大祚栄が王権を樹立して以来、926年に契丹の耶律阿保機に降るまで15代のおよそ229年の歴史をもつ。その地理範囲は建国の初期から最盛期の第10代の代仁秀の治世を経て末期に至るまでに伸縮はあるが、ほぼ今日の中国東北部の三省(遼寧省、吉林省、黒竜江省)を包み込み、南に下っては朝鮮半島の平壌付近の範囲である。この広範囲の地理からして、渤海史は現代の歴史意識におおいに関わってくる。北朝鮮、韓国、中国の歴史学会では渤海史を自らの民族史に引きつけ、これを同化して理解する傾向が強い。2024/07/04
bapaksejahtera
7
渤海に関する一般向けの書籍として数少ない著作である。古畑徹著「渤海国とは何か」は国家としての性格などを中心に述べた対して本書は3世紀に及ぶ大氏渤海の変容を通史的に述べる。本書を先に理解した上で古畑本に手を付ければよかった。中華領域は北からの強いエネルギーを取り込みつつ拡大した。圧倒的な波に抗し領域を維持した渤海は無視できない。数十回に及ぶ同国からの遣日本使とその規模、入京を拒まれた使いを入れれば莫大な渤海人の来訪があった。我が国に留まって渤海語教授を職とした者すらいる。日本海の重要性はこういう所にも表れる2020/07/29
竜王五代の人
6
墓の壁画とか、墓碑からの情報もあるのだけれども、中心となるのは唐・日本・新羅他の周辺諸国の史書で、そうすると結局外交史になってしまって渤海国がどんな国なんだか見えてこなかった。考古学の研究成果が足らないんじゃないかな。新羅とは戦争こそしないものの没交渉、唐には朝貢、日本とは外交に名を借りた交易で、日本の遣唐使に匹敵するような難破率なのに渤海国は積極的なのがすごい。エミシとの関係は?2024/06/10
-

- 和書
- 法人後見実務ハンドブック