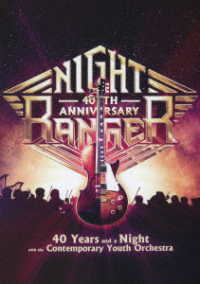出版社内容情報
平安時代から鎌倉時代へ、激動の時代を生きた仏師運慶。定朝様の穏やかな仏像に対して、躍動感にあふれる清新な作品を生みだし、歴史の檜舞台に登場した。残された日本を代表する仏像を通して、運慶の真の価値、古代・中世の仏師の世界と日本の仏像の魅力を、現場からの最新の研究成果にもとづいて明らかにする、今日の視点からの新しい仏像論。,
内容説明
日本を代表する仏師運慶は、古代から中世への激動期に、清新な表現の仏像を生みだし、檜舞台に登場した。現場からの最新の研究成果にもとづいて、運慶の作品の本質と、日本の仏像と仏師の魅力を明快に説いた仏像論。
目次
運慶の魅力―プロローグ
運慶とその父
新しい表現
時代の要請
南大門二王像
組織の長
運慶と日本の彫刻―エピローグ
著者等紹介
副島弘道[ソエジマヒロミチ]
1952年神奈川県に生まれる。’79年東京芸術大学大学院美術研究科修了。現在、跡見学園女子大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chanvesa
21
東大寺の金剛力士像について「二王像の表現は力強い運慶風で統一されている。そこに見られる多少の作風の差は、一組の像としての許容範囲にある。しかし、二体の作風に違いを認めるとすれば、それは運慶と快慶のあいだの微妙な距離がもたらしたものだ。」(144頁)運慶が許容したという懐の広さ。そして、快慶が同世代の芸術家として、ぎりぎりまで抑制しつつも、ほとばしった自己表現は、運慶への複雑な思いなのか。また、これぞ鎌倉といった荒々しく力強い表現から、晩年には異なった顔を見せていたこと(無著・世親立像)が興味深い。2025/07/20
SK
2
運慶展の予習。作品論が多くて、初心者向きではないかなぁ。2017/09/30
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢に転生したら氷の公爵様との溺愛…