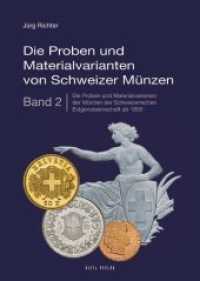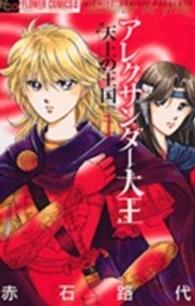内容説明
天平文化の花開いた奈良の都で、皇位継承権を持った天武天皇の子孫たちは、藤原氏の専権に反感を持つ氏族の策謀に巻き込まれ、次次と滅ぼされていった。数々の政変劇の実態を通して、日本古代国家の権力構造を探る。
目次
はじめに―吉野宮の誓盟から
律令国家の権力構造と皇親
奈良朝前期の政変と皇親
奈良朝後期の政変と皇親
奈良朝末期の政変と皇親
結語に代えて―奈良朝の政変劇と皇親
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
マカロニ マカロン
8
個人の感想です:B。今回の改元の元となった大伴旅人の催した「梅花の宴」は730年。奈良時代のことで、万葉集巻五のあの序文を見ると随分優雅な和歌会をしているようにも思えるのだが、その前年の729年には「長屋王の変」が起きている。長屋王を排除したい聖武天皇や藤原氏にとって邪魔な長屋王派の大伴旅人を太宰府に赴任させクーデターを実行した。更にその前年728年には妻を亡くしており、重苦しい気分の中での宴だった。そこから採られた「令和」は血腥い政変劇が相次ぐ奈良朝を背景を持つが、その再現はごめん被りたい。2019/05/23
遊未
3
いつの時代も最高権力者に近い存在(皇親)の生きにくさ。よく読んでみれば天武以降は同等の存在感のある天皇はいないように思えます。単純に被害者と思っていた長屋王にもそれなりの認識間違いがあったようです。有力者との関係思惑でで皇親が何が何だかわからぬ間に罪人にされてしまう時代。人によってはそれが一生のうちに何度も…という方もいました。2017/08/23
チャック
2
昔読んだが 天上の虹を読んだせいか?また読んでしまった。 奈良時代小説好きには真実と虚実を知るガイドブックだ。(間違った読み方かな?)図書館本なので、買おうかと思ってる。2020/03/03
源義
1
皇親は律令体制初期に諸臣の高位者が少なかった時にとりあえず高位者のポストを埋めるためのもの。故に蔭位の制が稼働し始めれば、その立場は王権の勿論藩屏などではなく、無能で危険な「前時代の遺物」に過ぎない。という視点から奈良時代の政治的事件(とそれに巻き込まれた皇親)を一つ一つ取り扱う。 それぞれの皇子の二世三世を追跡する手法はわかりやすいが、最終的に表に纏めてもらいたかった。また新田部皇子始め母系の問題も追跡すべきであり、1998年刊行ということで筆者もまだ若かったのかなと思う。2024/06/30
ひろただでござる
0
皇親が多くても少なくても天皇の地位は危うかったんや…その皇親も皇親というだけ(いや大変なことやと思うが)で毀誉褒貶が付き纏うって。「人民の幸福を願って謀反を起こす支配者など歴史上ほとんどあり得ないのである」の一文には笑ってしまうが、恵美押勝の乱が天皇単独王権が始まる端緒だったとは…やはり社会体制の変化というものは起きるときは一挙に起きてしまうものなんだ…と。2017/06/16