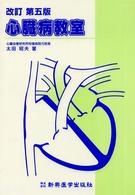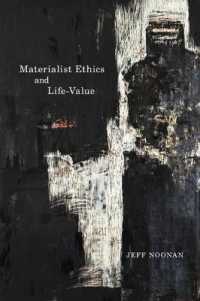内容説明
お茶は、日常茶飯事といわれるほど日本人の暮らしに根づいている。かつての庶民の茶=番茶を求めて国内のみならず海外まで行脚し、産地・製法・利用法を比較分析する。列島文化の成立ちを、番茶を通して描く日本文化論。
目次
番茶をもとめて
食べるためのお茶
茶を飲む女たち
お茶が仕分けるウチとソト
番茶から煎茶へ
東アジアの茶と日本の茶
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
6
番茶といえば安い茶、焙じ茶位に認識する現代人にとって、茶は禅僧が近世になって広めた物と観念するのが普通である。著者は野生茶さえ有する我が国の茶文化が東南アジアの一部と同様食生活そのものと強く結びついた物であった事を明らかにする。穀物を無駄なく摂取するには煮出したり炊いたりするよりは煎ってα化させ粉体にし、これを茶などを泡立てた物で摂取する事が効率的であるかは理解できる。TVなどでは食物がどのようにして作られるか滑稽なほど無知な人間が出現する。日常茶飯の記憶もその習慣の衰退とともに簡単に忘失するのであろう。2020/09/25
のんき
5
1998年9月刊。現代ではお茶=煎茶というイメージだけど、煎茶がこれほど普及する以前に日本人の暮らしと結びついていたお茶=番茶について考察したもの。日常的で身近でありすぎる故、文献や伝承として残るものは少なく、多くは推察するしかないもどかしさと不確実さはあるものの、細い糸を辿り紡いでいこうと海外まで足を延ばした著者の熱意は半端ない。2011/08/26
印度 洋一郎
4
いわゆるエリートの文化である"茶の湯"とは異なる、庶民の味・番茶のディープな世界を探る一冊。恐らく煎茶よりも古く伝来し、広く定着したにも関わらず記録にも残らず、今では各地の山里に細々と残るのみという番茶文化を、炒る、煮る、蒸す、そして食べるという製造方法に着目しながら訪ね歩く。著者によると、"茶"とは元々食事と同義語だったという。農作業の間食として軽食と共に食する、濃い味のスープみたいな茶は、自分の町にもあるのでちょっと驚いた。日本の番茶文化の源流が、チベットやミャンマーの奥地にも存在しているのもビックリ2011/12/07
takao
2
食べる茶でもある。2021/07/27