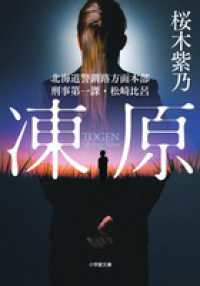内容説明
いつの世もどこの世界でも、権力者に対する批判は存在する。幕政・幕閣を戯評し、人々の喝采を受けた風刺画は、時には厳しく断罪された。作者・板元の意図、民衆の評判などを総合的に捉え、江戸世相史の一面を鋭く描く。
目次
現代と江戸の風刺画
消費者金融問題のはじまり
金権の時代と世直し大明神
寛政改革への批判
歌麿・豊国・一九の筆禍
天保改革と風刺画
弘化・嘉永期の風刺画
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
果てなき冒険たまこ
3
浮世絵の本を読んだり勉強したりしてると必ず登場するのが田沼意次と水野忠邦。どっちも幕政を改革しようとして民衆には不人気だったのはみんな知ってるけどじゃ実際にはどんな改革でどんなにみんなが迷惑していたのか説明されていることはほとんどない。よく浮世絵師が「反骨」とか言われるけど実際がわからないなぁと思っていたけどやっと説明されたよ。ようやくなんで国芳の「源頼光公館土蜘作妖怪図」があんなに話題になって爆発的に売れたかがやっと分かった。物事表面だけじゃ何もわかんないね。2025/06/08
やまだてつひと
3
江戸時代の風刺画 特に水野忠邦等が妖怪として描かれており、それを判別するために家紋を入れたりするなどして、分かる人には分かる書き方をしていたようだ。それはお上が出版物を検閲をしていた為であり、直接的な表現を避けていたのだと思う。風刺画ではないが、ロシアのアネクドート等は、口頭で伝聞するため、「妖怪」のような空想上のキャラクターはあまり登場しないので、その差はかなり面白かった。特に受け手側が独自の解釈をしていくというスタイルは、アメリカンジョークやアネクドートといった海外の風刺とはかなり違う点は留意したい2024/05/21
印度 洋一郎
2
現在の漫画のそもそもの原点とも言うべき風刺画。落書きみたいなものなので、とても後世に残り難いが、江戸時代になると出版産業の勃興のお陰で、商業出版物として流通したものが残っている。この本では、18世紀末の田沼時代からの風刺画を扱っているが、やはり田沼意次と水野忠邦(天保の改革の)ネタが多い。この二人、よほど庶民の恨みを買っていたと見えて、"怪物"扱いの画ばかり。これを見ていると、まるっきり現在の新聞の政治蘭の一コマ漫画の源流だ。「はんじもの」と呼ばれる、絵に隠された暗喩を読み説く作品も面白い。2011/08/17
-

- 和書
- 戦中派の懐想