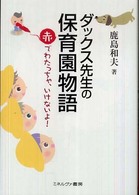出版社内容情報
家族形成が底辺層に達し、病気治しや亡魂慰撫の要求が高まった19世紀初頭、尾張国熱田で元奉公人の女性によって創唱された如来教。民衆宗教・新宗教の嚆矢とされる同教は、いかにして誕生したのか。流行中の金毘羅信仰や浄土系・法華系の仏教的世界観を摂取しつつ、互恵的伝統の継承・再構築を志向した経緯を追究し、民衆宗教の出自を解き明かす。
内容説明
家族形成が底辺層に達し、病気治しや亡魂慰撫の要求が高まった十九世紀初頭、尾張国熱田で元奉公人の女性によって創唱された如来教。民衆宗教・新宗教の嚆矢とされる同教は、いかにして誕生したのか。流行中の金毘羅信仰や浄土系・法華系の仏教的世界観を摂取しつつ、互恵的伝統の継承・再構築を志向した経緯を追求し、民衆宗教の出自を解き明かす。
目次
序章 如来教像再構成の課題と展望
第1章 教祖の前半生と民間宗教者への社会的期待
第2章 「日待空間」の形成と展開
第3章 如来教の組織的展開と中核的教説
第4章 応答を直接的契機とする宗教思想の形成と展開
第5章 如来教の成熟
第6章 教祖の晩年以降における近世社会と如来教
終章 民衆宗教・新宗教の「祖型」としての如来教
著者等紹介
神田秀雄[カンダヒデオ]
1949年東京都に生まれる。1983年一橋大学大学院社会学研究科地域社会研究専攻博士後期課程単位取得退学。天理大学人間学部教授、博士(社会学・一橋大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。