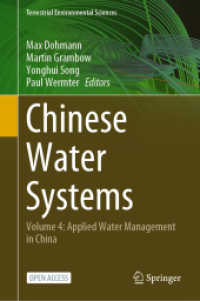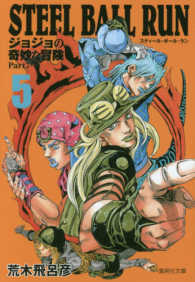内容説明
徳川家康が入国したころの江戸は、どのような姿をしていたのか。いまだ不明な点が多いその様相を、地形環境や遺構群を素材に描き出す。また、土木技術の側面から、江戸が都市としていかに開発されてきたのかを考える。
目次
江戸の地形環境―武蔵野台地と利根川デルタ
「静勝軒寄題詩序」再考
「江戸」成立前夜の山の手地域―中世後期の村落と水資源
徳川家康の江戸入部と葛西
丸の内を中心とした近世初頭の遺跡について
小石川本郷周辺の自然地形と近世土木事業の実態
江戸を支える土―西久保城山土取場跡
江戸、下町の造成―東京都中央区の遺跡を中心として
江戸城をめぐる土木技術―盛土と石垣構築
近世における石積み技術
近世をきりひらいた土木技術―胴木組と枠工法護岸施設
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
朗読者
15
昔、徳川家康以前の江戸は湿地・寒村だったと習ったが、15世紀、太田道灌の時代にはすでに屈指の港湾都市だったとの指摘は新鮮だった。先入観を払拭せねば。前半は地形と交通と町の関係などに着目し、後半は石積や枠工法護岸などの土木技術に着目して書かれており、大局的にも技術史にも勉強になった。陸路と水路の結節点となる橋周辺に町ができた、との指摘になるほどと思った。2025/02/08
もるーのれ
2
家康の江戸入府の頃の江戸の自然環境や土地利用の状況、そして幕府成立後の土地開発の状況などに関する論考。特に、低地を居住できる環境にするための様々な土木技術や幾重にも亘る造成工事の痕跡には、驚かされるばかりである。これを大した機械も無い時代にやったとは、先人には本当頭が下がる。2023/01/02