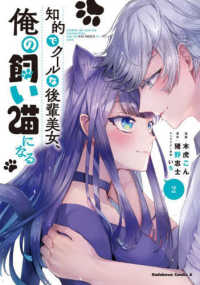出版社内容情報
15?17世紀の日本列島の山野は、鉱物・森林・水など豊富な資源をもたらす一方、地震・水害が頻発した。地域社会はその二面性とどう向き合ったのか。甲斐国の事例を中心に、資源の調達・利用や自然災害への対応を追究し、村落間ネットワークの様相を解明。災害史料の成立・継承にも着目し、現代にも通じる自然環境と人間との関係を再考する。
内容説明
一五~一七世紀の日本列島の山野は、鉱物・森林・水など豊富な資源をもたらす一方、地震・水害が頻発した。地域社会はその二面性とどう向き合ったのか。甲斐国の事例を中心に、資源の調達・利用や自然災害への対応を追究し、村落間ネットワークの様相を解明。災害史料の成立・継承にも着目し、現代にも通じる自然環境と人間との関係を再考する。
目次
序章 環境史・災害史研究の軌跡と本書の構成
第1部 水資源と災害(室町期甲斐国における井堰の築造;戦国期の地域寺社における井堰築造と景観;戦国期東国の地域社会と水資源;近世御勅使川流域における川除普請)
第2部 山野における資源の調達(中近世移行期の土豪と地域社会;戦国期における竹木資源の保全と調達;山地領有の由緒と文書;丹波国山國・黒田地域における鮎漁の展開)
第3部 災害史料の成立と継承(甲斐国湖水伝説の成立;室町・戦国期の列島内陸部における地震災害;戦国期上野国赤城山における富士浅間神の勧請;富士山宝永噴火に関する資料の記録化)
終章 中近世の資源と災害
著者等紹介
西川広平[ニシカワコウヘイ]
1974年神奈川県に生まれる。1996年中央大学文学部史学科国史学専攻卒業。2011年中央大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(史学)。山梨県立博物館学芸員等を経て、中央大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。