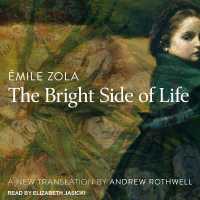内容説明
縄文時代から南北朝期まで、日本における音楽とその制度の変遷をたどる。平安時代の殿上人と民衆の音楽、鎌倉幕府と雅楽、宮廷儀式の中の雅楽・舞、楽人の系譜などを追究。広い視点から音楽の歴史を明らかにする。
目次
序章 古代音楽の研究と課題(古来の歌舞と外来の楽舞;音楽制度の変遷と楽家の成立 ほか)
第1章 雅楽の変遷と音楽文化の展開(雅楽―宮廷儀式楽としての国風化への過程;平安末期における音楽文化の展開 ほか)
第2章 宮廷儀式と雅楽(相撲儀式と楽舞―乱声・厭舞を中心に;宮廷儀礼の中の舞―女楽・女踏歌・五節舞 ほか)
第3章 楽人の系譜とその活動(古代の笛と「笛吹」について;地下楽家大神氏の系譜とその活動 ほか)
著者等紹介
荻美津夫[オギミツオ]
1949年北海道に生まれる。1978年北海道大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。新潟大学人文学部教授、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。